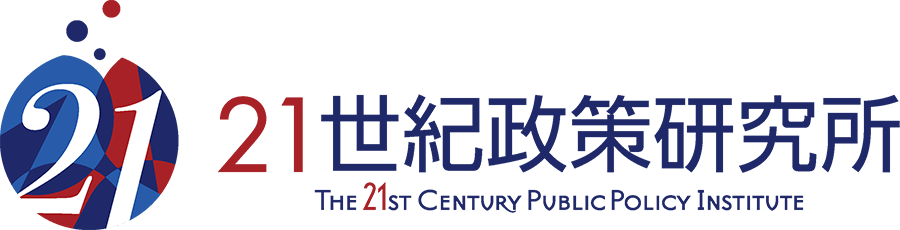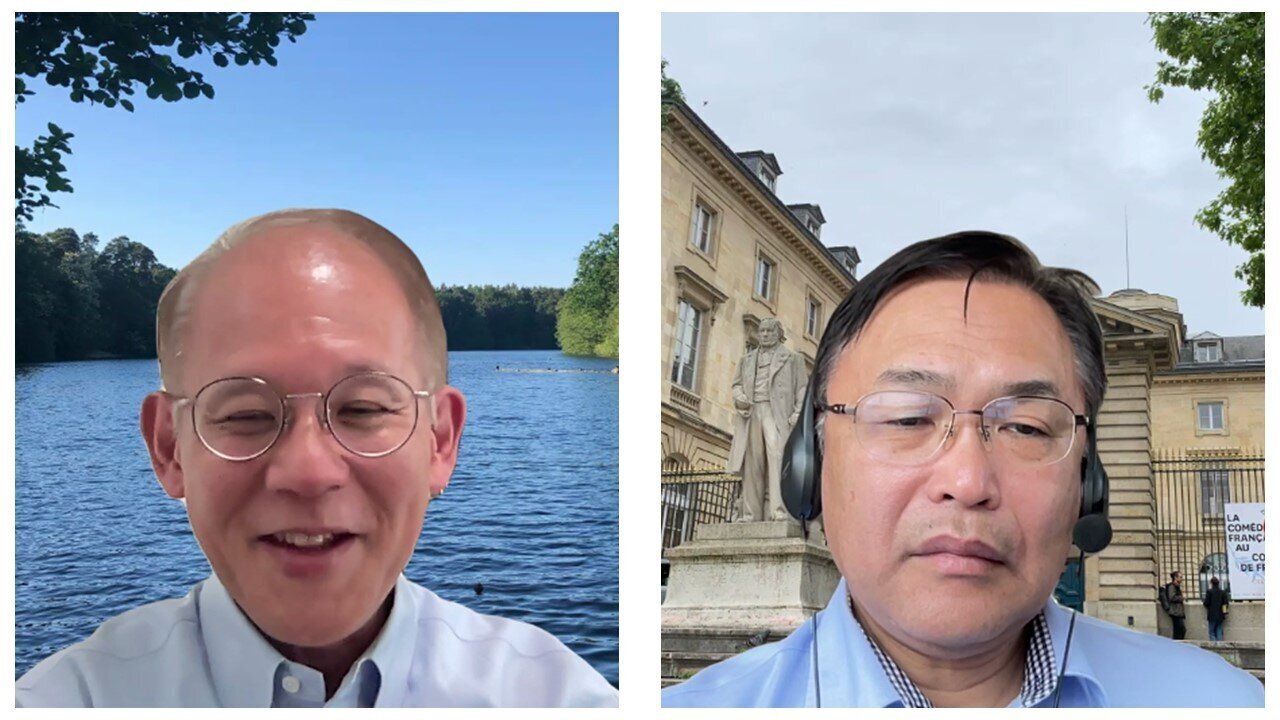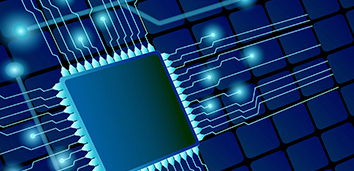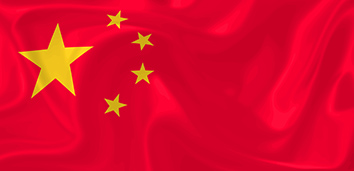シンポジウム「転換期中国の国家戦略~先端産業育成と社会保障改革」を開催しました

左から、川島研究主幹、丁研究委員、片山研究委員
経団連総合政策研究所(筒井義信会長)の中国情勢研究プロジェクト(研究主幹=川島真東京大学大学院総合文化研究科教授)は7月2日、シンポジウム「転換期中国の国家戦略~先端産業育成と社会保障改革」をオンラインで開催しました。
前半は研究委員2人が講演。後半は川島研究主幹がモデレーターとなって、研究委員2人とパネル討議を行いました。概要は次のとおりです。
■「新型挙国体制」と中国における先端産業の発展 丁可研究委員(ジェトロ・アジア経済研究所主任研究員)
中国は新型挙国体制を基盤に先端産業の育成を進め、電気自動車(EV)やAIなど多くの分野で世界をリードしている。この体制は旧来の政府主導と異なり、市場原理を併用した点に特徴がある。
地方政府の政策イニシアティブと民間テック企業への支援を通じ、科学研究費や補助金による巨額の資金供給、EV産業に代表されるサプライチェーンの戦略的整備、先端技術の社会実装が推進されてきた。
しかし、地域間競争の激化は過剰生産につながっており、内需低迷による輸出依存度の高まりは貿易摩擦の原因となっている。不動産バブル崩壊による地方政府の財政難が産業支援の持続可能性を脅かしていることなども課題であり、現在の中国では産業政策は万能薬となっていない。
■人口減少社会に転じた中国で、 社会保障制度改革の重点はどう変わっているか 片山ゆき研究委員(ニッセイ基礎研究所保険研究部主任研究員)
中国は2034年に超高齢社会へ移行すると予測されている。社会保障関係費は過去10年で3倍に急増しており、特に年金が財政に大きな影響を与えている。
財政制約のもと、中国の社会保障制度は、公的な制度運営や加入促進に民間企業を活用する「福祉ミックス体制」を構築している。民間活用例には、介護保険の民間保険会社との共同運営、フードデリバリー企業によるギグワーカーの社会保障負担などがある。
政府も年金財政の安定化のため、年金受給開始年齢を引き上げるほか、年金制度における地域間の財政格差是正のため、余剰のある地域から不足地域へ財源を移転している。
社会保障については、国民の生活を安定させることで消費を喚起する役割が期待されるが、現実には将来不安を払しょくできず貯蓄志向が強まっている。
■パネル討議
両研究委員の発表をふまえ、川島研究主幹は、先端産業政策と社会保障は、経済成長を巡る中国政府の財源配分におけるジレンマであると指摘。対米競争や国家の能力構築を目指す方針などを背景に、先端産業に投資が集中する一方で、社会保障の財源を圧迫していると述べた。
そうしたなか、中央政府および地方政府の財政負担のあり方の見直しも、今後の重要な課題になると言及。アクセルとブレーキのような両領域のバランスをいかに保つかは、日本を含む先進国と共通する課題であり、日本も中国の状況から学ぶことができる部分があると総括した。