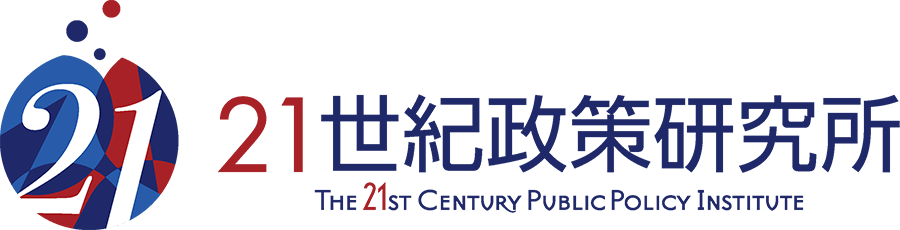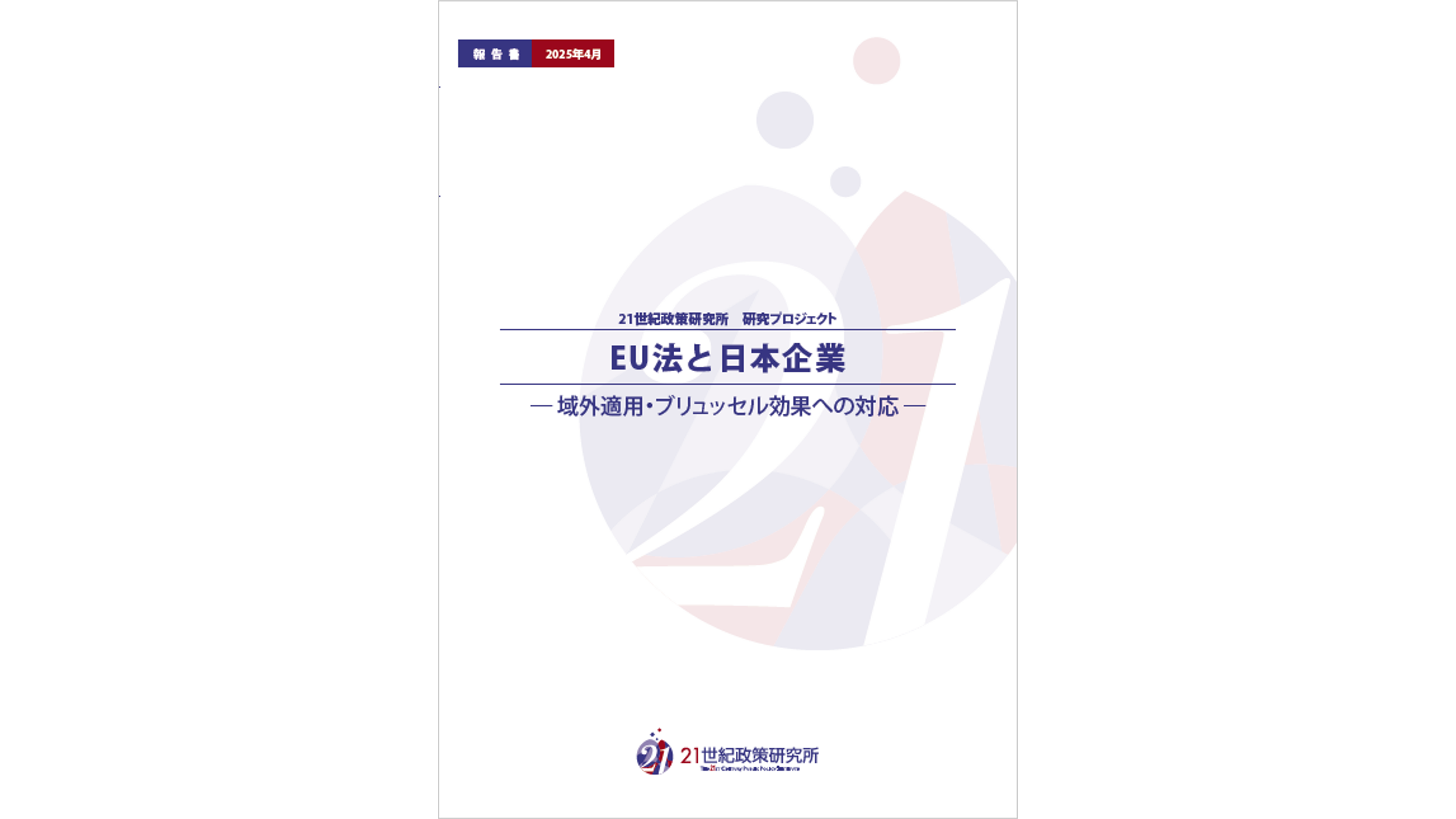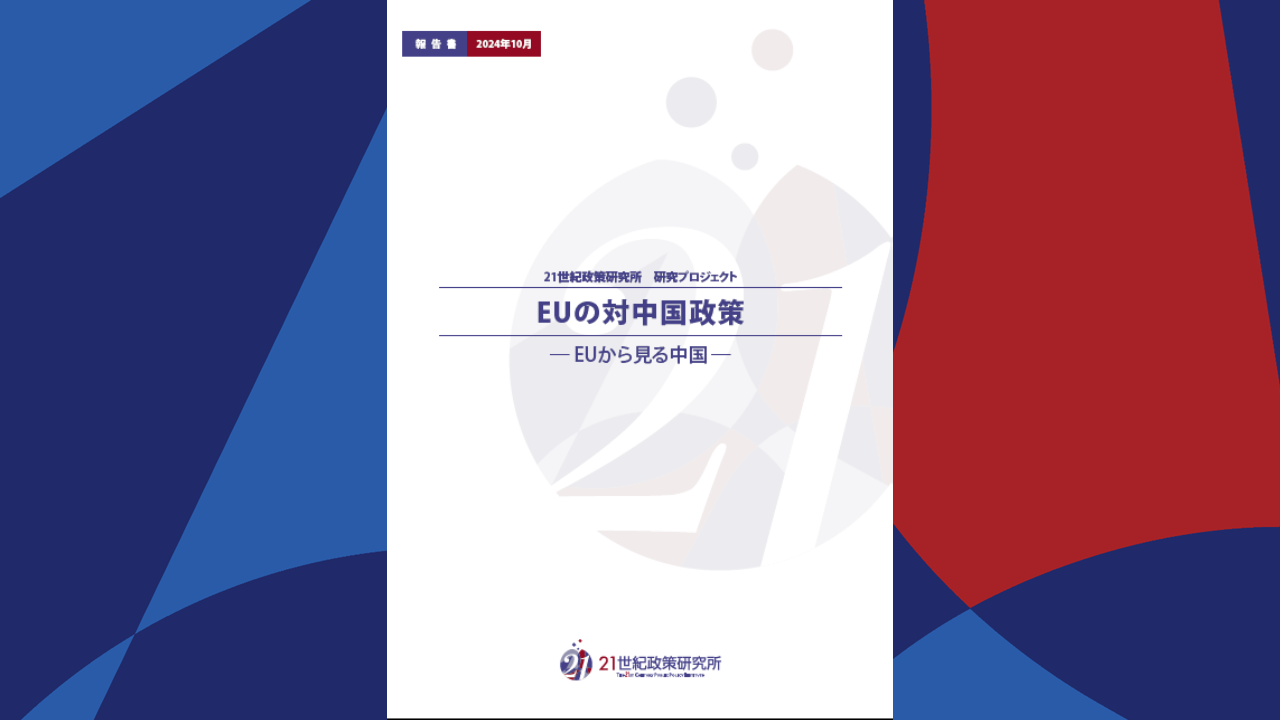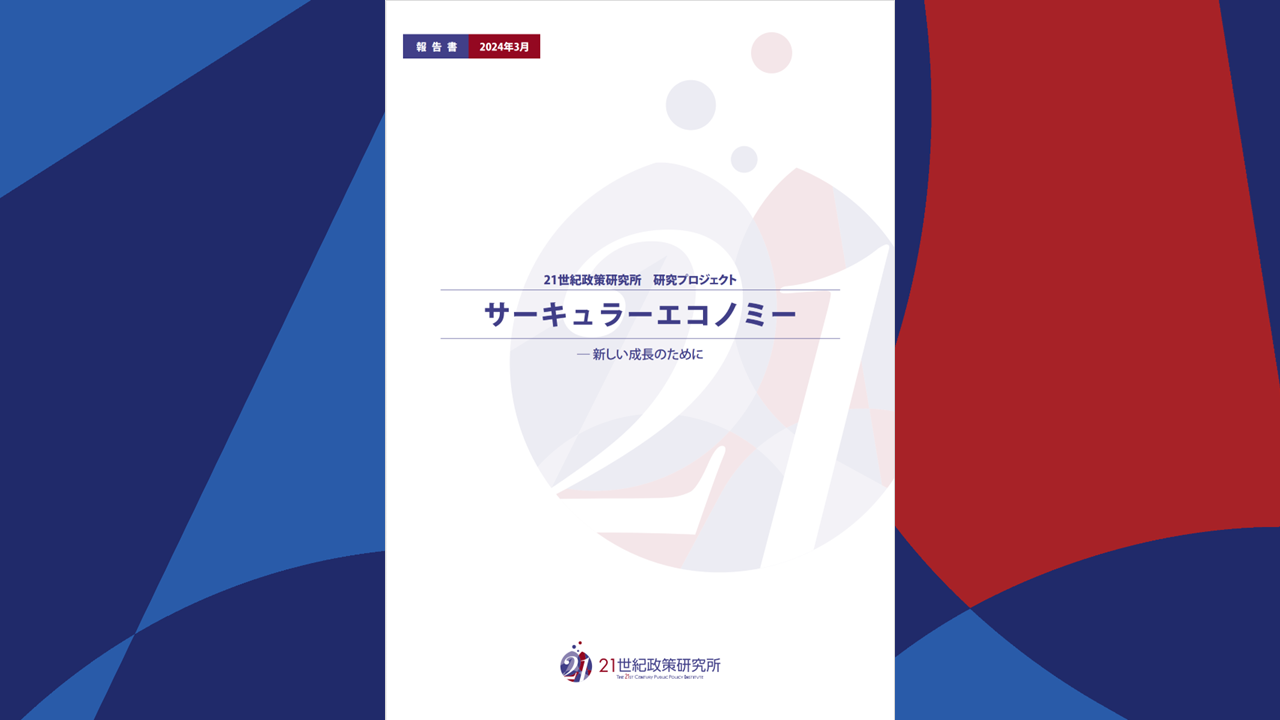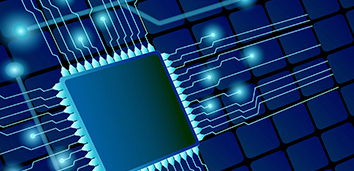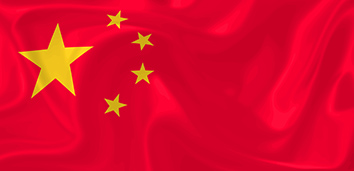2025/08/28
セミナー「トランプ2.0政権の下の米欧関係」を開催しました

遠藤教授(左)、伊藤特任研究主幹(右)
経団連総合政策研究所(筒井義信会長)の欧州研究プロジェクト(特任研究主幹=伊藤さゆりニッセイ基礎研究所経済研究部常務理事)は7月14日、東京大学大学院法学政治学研究科の遠藤乾教授を招き、セミナー「トランプ2.0政権の下の米欧関係」をオンラインで開催しました。
伊藤特任研究主幹は冒頭、トランプ政権の再登場が世界経済に与える影響を共通の切り口として、欧州情勢を専門家と共に多角的に分析するセミナーを開催していく方針を示しました。
セミナーではまず遠藤氏が講演し、続いて伊藤特任研究主幹が遠藤氏に質問する形で議論を深めました。概要は次のとおりです。
■トランプ2.0政権下の欧州秩序~EU‐NATO体制の行方(遠藤氏)
「EU‐NATO体制」はウクライナ戦争を契機に一時的な結束を見せたが、再び揺らぎが生じている。現在のEUを「際・外・内」の三つの視点から見ると、その複雑な状況が浮かび上がる。
「際」では、ウクライナ戦争が続いており、欧州は安全保障の最前線に立たされている。米国の支援が不確実ななか、EUが自ら対応する覚悟と能力が問われている。ウクライナのEU‐NATO加盟を巡っては、分権的な国家構造や汚職、予算負担などの課題が指摘され、特に北大西洋条約機構(NATO)加盟に関しては第5条の集団防衛義務が障壁となっている。
「外」では、トランプ政権という域外パワーが大きく影響を及ぼしている。トランプ政権は多国間主義や自由貿易に否定的で、ロシアとの接近や欧州の極右政党「AfD(ドイツのための選択肢)」との関係も報じられている。これは欧州の信頼を揺るがす動きである。
「内」では、ポピュリズム勢力の台頭が進んでいる。ドイツ、フランスなど主要国でEU懐疑派の支持が政権の成立に不可欠となる可能性があり、EUの統合維持には不安が残る。今のところ体制は持ちこたえているが、緊張は続いている。
日本への含意としては、外国人問題が極右の足音とともに現実化しつつある点が挙げられる。厚生労働省の統計では、国内の外国人数は約370万人、年間流入は33万人超。英国のブレグジット前と同水準で、日本も類似の局面にある。出入国管理及び難民認定法(入管法)改正で家族の呼び寄せも可能となり、今後、外国人数は700万〜1000万人規模に達する可能性がある。
一方、日本には年収186万円以下のアンダークラスが約1000万人いる。その上にローワーミドル層が2000万〜3000万人存在することも重要である。時系列的にも右傾化が進むなか、外国人包摂や貧困層対策だけでなく、ローワーミドル層も同時に捉えた視点が求められる。
■対談
続く対談では、米国の国際秩序からの後退やポピュリズムの拡大が欧州に与える影響、安全保障体制の再構築、経済統合と財政連携の可能性について議論を深めた。
ドイツの国防強化と英国、フランスとの連携、EUによる安全保障基金創設や共通債発行の構想が注目される一方、各国の脅威認識や役割分担意識の違いが統合の足かせとなっていると指摘された。加えて、NATOの集団防衛原則を巡る米国の姿勢や、EU・NATOのコンセンサスを揺るがす政党の動きにも懸念が示された。
その他、EU全体での軍備統合には制度的な進展がある一方で、構造的な限界もあるとの見方が示された。
伊藤特任研究主幹は冒頭、トランプ政権の再登場が世界経済に与える影響を共通の切り口として、欧州情勢を専門家と共に多角的に分析するセミナーを開催していく方針を示しました。
セミナーではまず遠藤氏が講演し、続いて伊藤特任研究主幹が遠藤氏に質問する形で議論を深めました。概要は次のとおりです。
■トランプ2.0政権下の欧州秩序~EU‐NATO体制の行方(遠藤氏)
「EU‐NATO体制」はウクライナ戦争を契機に一時的な結束を見せたが、再び揺らぎが生じている。現在のEUを「際・外・内」の三つの視点から見ると、その複雑な状況が浮かび上がる。
「際」では、ウクライナ戦争が続いており、欧州は安全保障の最前線に立たされている。米国の支援が不確実ななか、EUが自ら対応する覚悟と能力が問われている。ウクライナのEU‐NATO加盟を巡っては、分権的な国家構造や汚職、予算負担などの課題が指摘され、特に北大西洋条約機構(NATO)加盟に関しては第5条の集団防衛義務が障壁となっている。
「外」では、トランプ政権という域外パワーが大きく影響を及ぼしている。トランプ政権は多国間主義や自由貿易に否定的で、ロシアとの接近や欧州の極右政党「AfD(ドイツのための選択肢)」との関係も報じられている。これは欧州の信頼を揺るがす動きである。
「内」では、ポピュリズム勢力の台頭が進んでいる。ドイツ、フランスなど主要国でEU懐疑派の支持が政権の成立に不可欠となる可能性があり、EUの統合維持には不安が残る。今のところ体制は持ちこたえているが、緊張は続いている。
日本への含意としては、外国人問題が極右の足音とともに現実化しつつある点が挙げられる。厚生労働省の統計では、国内の外国人数は約370万人、年間流入は33万人超。英国のブレグジット前と同水準で、日本も類似の局面にある。出入国管理及び難民認定法(入管法)改正で家族の呼び寄せも可能となり、今後、外国人数は700万〜1000万人規模に達する可能性がある。
一方、日本には年収186万円以下のアンダークラスが約1000万人いる。その上にローワーミドル層が2000万〜3000万人存在することも重要である。時系列的にも右傾化が進むなか、外国人包摂や貧困層対策だけでなく、ローワーミドル層も同時に捉えた視点が求められる。
■対談
続く対談では、米国の国際秩序からの後退やポピュリズムの拡大が欧州に与える影響、安全保障体制の再構築、経済統合と財政連携の可能性について議論を深めた。
ドイツの国防強化と英国、フランスとの連携、EUによる安全保障基金創設や共通債発行の構想が注目される一方、各国の脅威認識や役割分担意識の違いが統合の足かせとなっていると指摘された。加えて、NATOの集団防衛原則を巡る米国の姿勢や、EU・NATOのコンセンサスを揺るがす政党の動きにも懸念が示された。
その他、EU全体での軍備統合には制度的な進展がある一方で、構造的な限界もあるとの見方が示された。