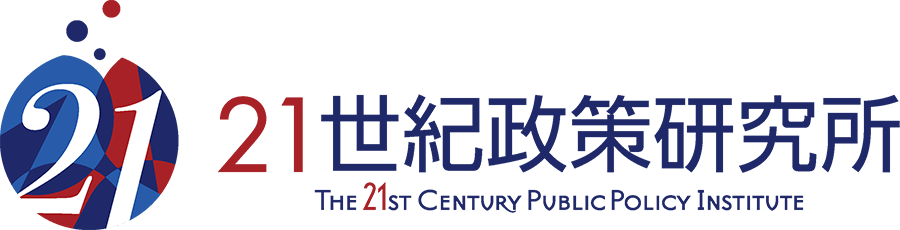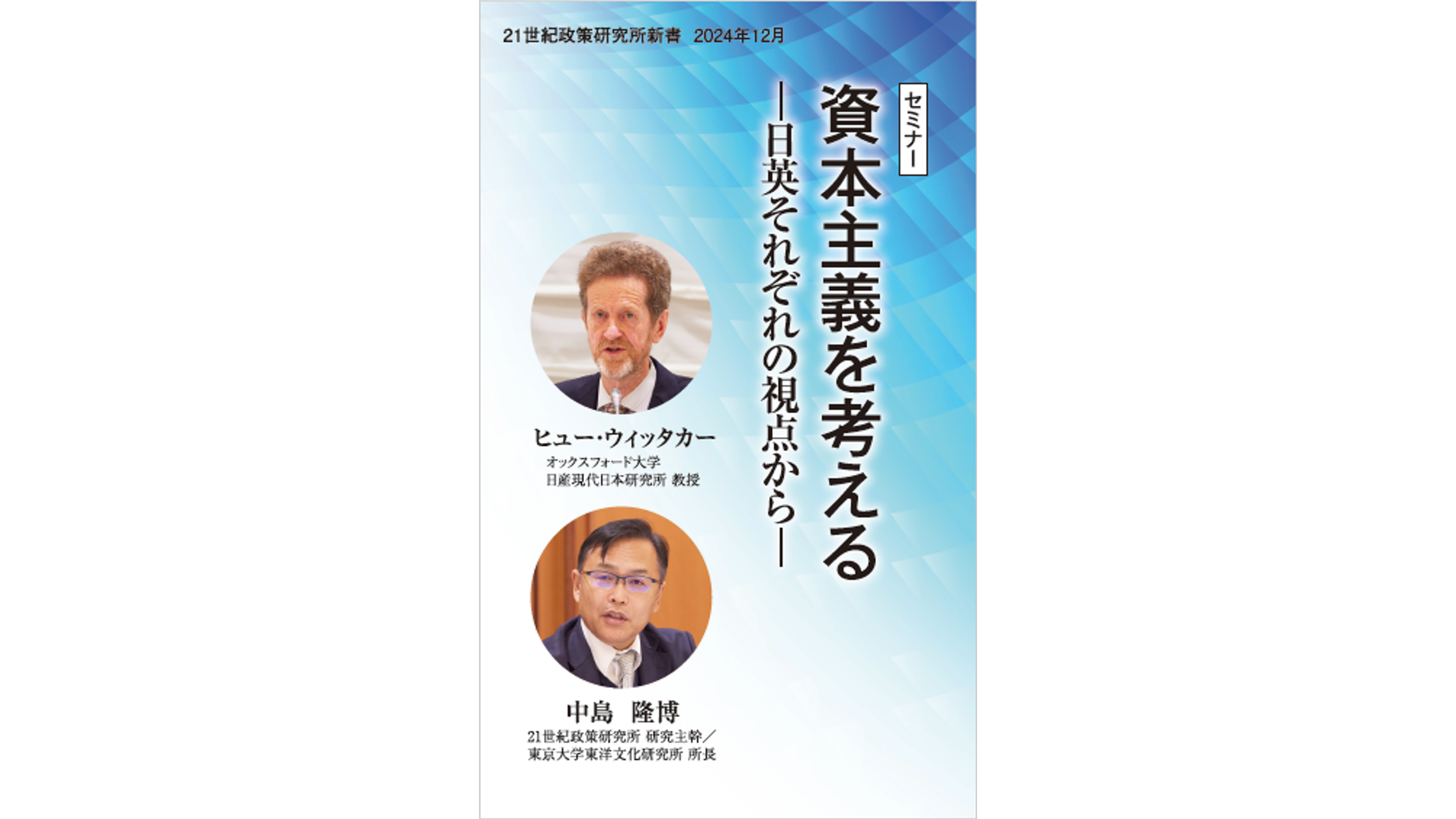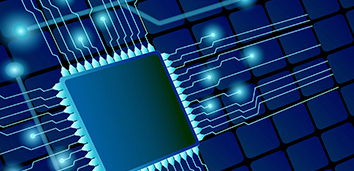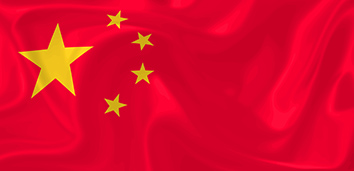セミナー「民主主義はどこへ向かうのか」第二弾を開催しました
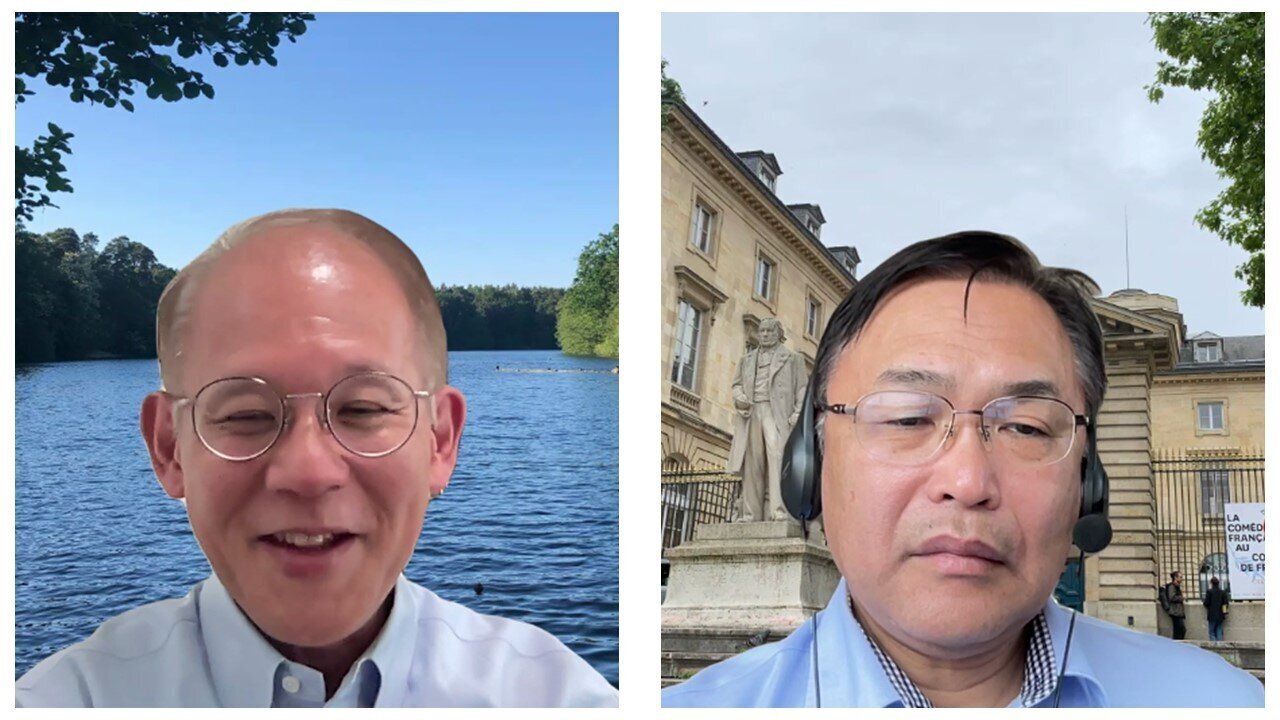
左から宇野教授、中島研究主幹
経団連総合政策研究所(筒井義信会長)の資本主義・民主主義研究プロジェクト(研究主幹=中島隆博 東京大学東洋文化研究所所長)は7月9日、東京大学社会科学研究所の宇野重規教授を招き、セミナー「民主主義はどこへ向かうのか」の第二弾をオンラインで開催しました。概要は次のとおりです。
■民主主義はどこへ向かうのか
1.民主主義の概念
民主主義の概念については混乱がみられるが、次のように整理できる。
まず、民主主義とは多数決のことだという意見がある。しかし、いつでも多数決を使ってよいわけではなく、少数者の権利の保護が確保されていることを前提としたうえで使うのが民主主義である。
次に、民主主義とは選挙のことだという意見がある。しかし、民主主義と選挙とは本来異質なものであり、選挙だけが民主主義ではない。現代において、国民は選挙に参加しているだけでは政治に参加しているとはいえず、政治が自分たちの意見を受け止めてくれないという不満が募っている。民主主義において一番大切な「参加と責任のシステム」(政治に参加するからこそ、そこで決まったことに責任を取るシステム)を、現代の代議制民主主義を通じて実現できるのかを考えていかなければならない。
民主主義には、議院内閣制・三権分立・選挙制度などの具体的な制度という側面と、終わることのない理念という側面がある。これらを結び付け、民主主義の具体的な制度化について、今後ますます自由に考えていくことが重要である。
2.歴史からみる民主主義の現在地
現在では、民主主義といえば主に代議制民主主義が想定されるが、起源である古代ギリシャの都市国家では、民主主義と選挙は決してイコールではなかった。アリストテレスは、むしろ民主主義と相性がいいのは抽選(誰もがランダムに公職に就く制度)であると言った。古代の民主主義と現在われわれが民主主義と呼んでいるものは似て非なるものなのである。
大統領制や議院内閣制といった現在の民主主義の制度は、1860年代に『代議制統治論』(J・S・ミル)や『英国憲政論』(ウォルター・バジョット)によって精緻化されたものに始まる。せいぜい160~170年程度の歴史しかない未完成な制度であって、もしかすると現在は代議制民主主義のあり方の転換期に当たるのかもしれない。
これまで民主主義の議論は、選挙制度改革など議会にフォーカスしたものが多かった。しかし、実際に多くの民主主義国において政治を動かしているのは行政(内閣や大統領府など)であるから、今後は、例えば市民が直接政策を提案したり情報公開を求めたりするなど、行政に対する民主的統制を強化する制度のあり方をより深く検討すべきである。
3.民主主義の意義とこれから
民主主義の是非については多くの議論がある。私は、民主主義の意義とは、①公開による透明性(政策が公開の場で透明なプロセスにより決定されることによって納得感が生まれ、事後的に検証することも可能となること)②参加を通じての当事者意識(自分たちのことを自分たちで決めているという実感に由来するエネルギーを引き出すことができること)③判断に伴う責任(人々に判断の機会を与え、同時に責任を持ってもらうこと)――にあると考える。
われわれはこれらを踏まえて今後を考えなければならない。米国という民主主義の祖国がこれを牽引しなくなり、民主主義は正しいのだ、いつか全ての国が民主化するのだ、という従来の大前提が揺らぎつつある時代において、それでも民主主義を選ぶのか、それとも見切りをつけるのか、真剣に考えるべき時期に来ているのである。
◇
セミナー後半では、宇野氏と中島研究主幹が対談し、米国の民主主義の仕組みや宗教との関係について議論を深めた。
参加者から、今後の新しい世界秩序について質問が出ると、宇野氏は、二国間関係・有志国間関係で秩序をつくるという思想が強くなるだろうが、米国がもう一度国際主義に戻ることもあるかもしれないと応じた。