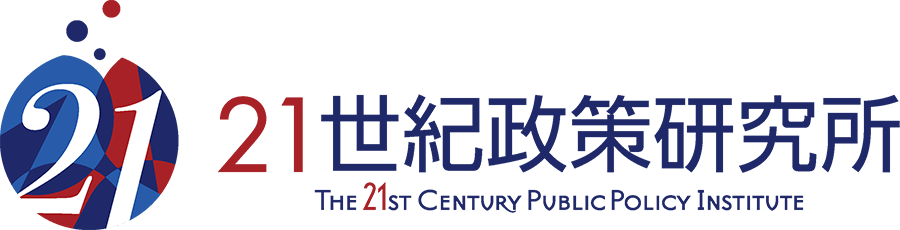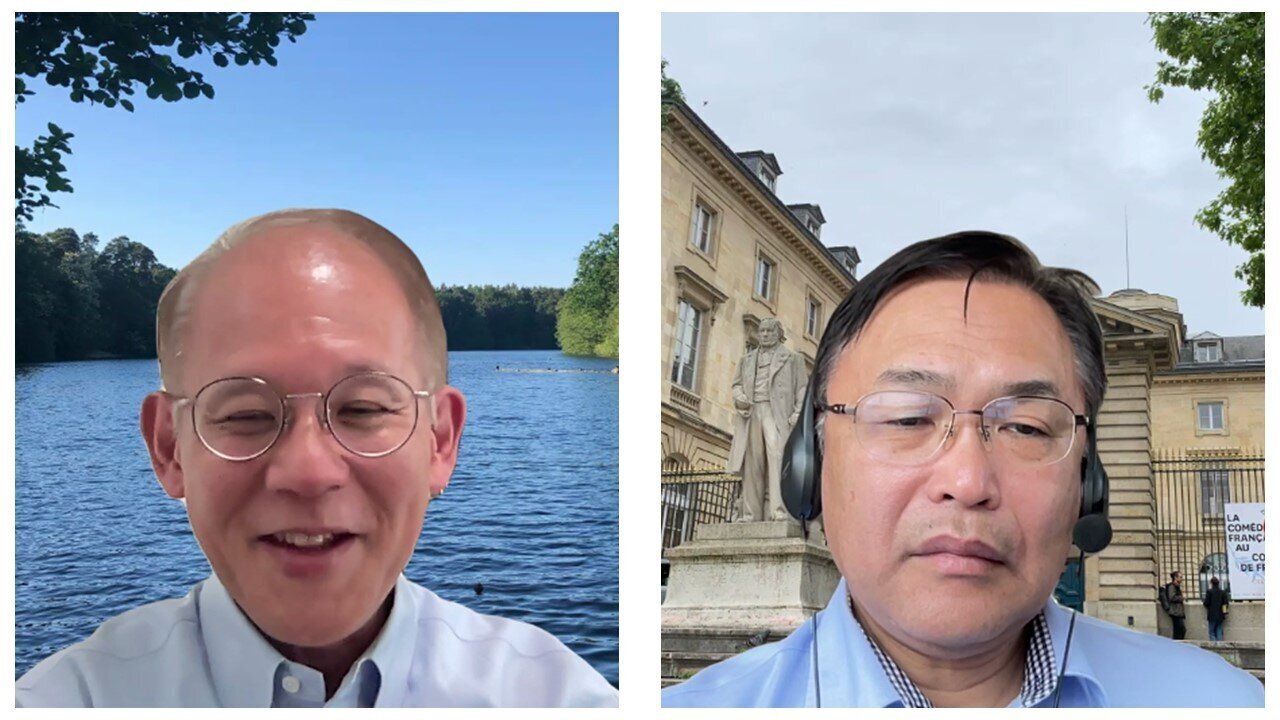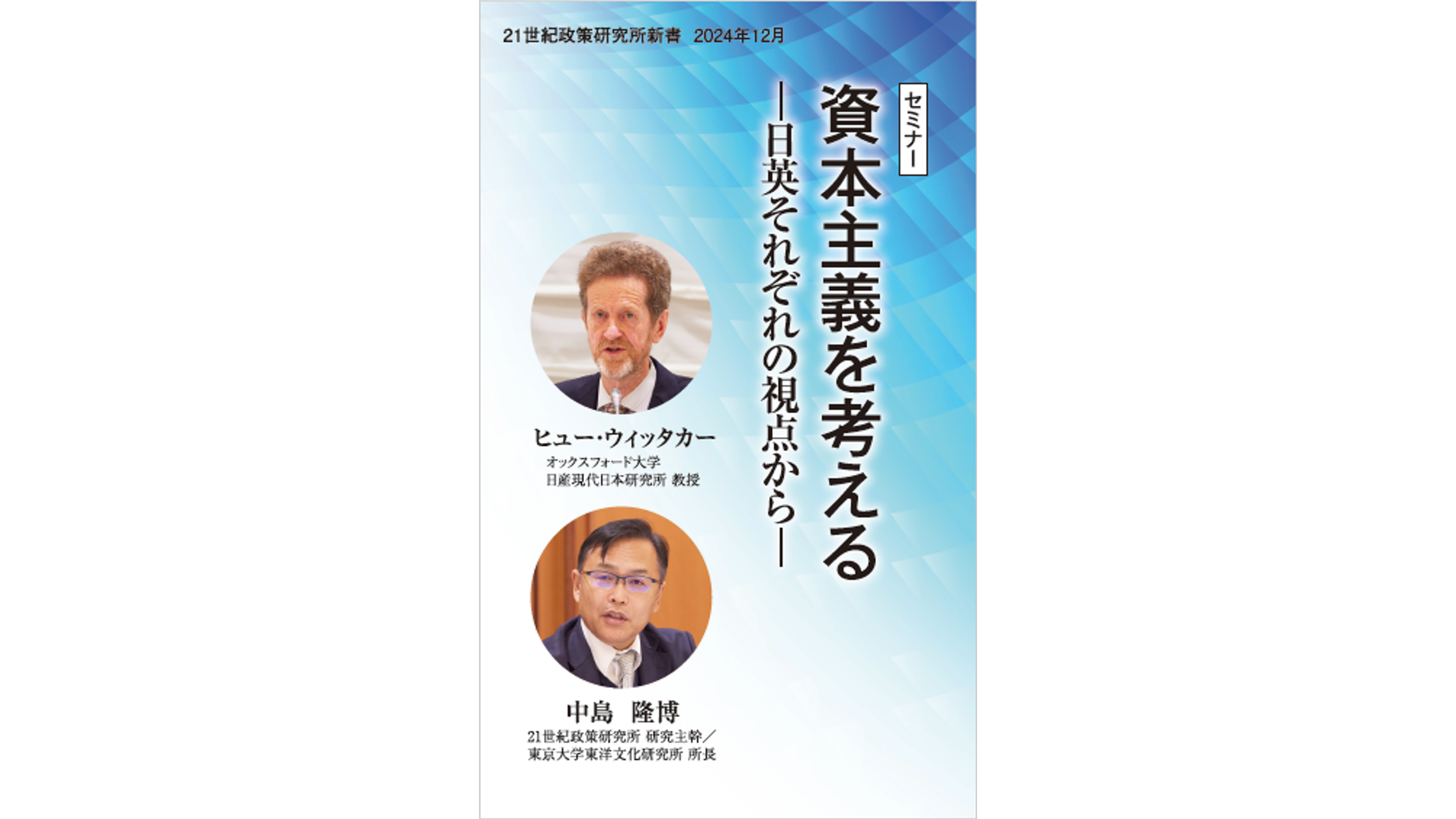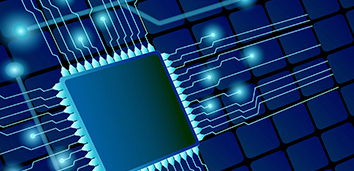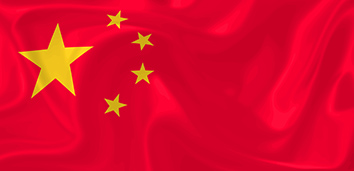オックスフォード大学を訪問しました

左下:ポール・コリア―教授、中央上:コリン・メイヤー教授、右上:ヒュー・ウィッタカー教授、中央下:中島研究主幹
「資本主義・民主主義プロジェクト」(研究主幹:中島隆博 東京大学 東洋文化研究所所長)」では、従来型の資本主義に起因する環境問題や格差問題、自由民主主義の危機が浮き彫りになる中でこれらを乗り越えるべく、資本主義のあり方や人間観・社会観のあり方を見直してアップデートしなければならないという問題意識のもと、哲学をはじめとするリベラルアーツの叡智の蓄積を活用しつつ研究を進めており、国内外の様々な分野の有識者と議論を行っています。
先般、当研究プロジェクトの一環として、中島隆博研究主幹が10月6日から9日にかけて、オックスフォード大学を訪問しました。
当研究プロジェクトにおいて複数回にわたり議論を重ねてきたマルクス・ガブリエル ボン大学教授が提唱する「倫理資本主義」概念は、「21世紀政策研究所 NEWS LETTER」(2024年6月号)でもご紹介しました。そのガブリエル教授の考えに大きな影響を与えた人物が、「パーパス経営」を提唱するオックスフォード大学のコリン・メイヤー教授です。そのほかにも同大学には、これまでの資本主義を分析したうえで望ましい資本主義のあり方などについて研究する教授が多数おられます。ここでは、コリン・メイヤー教授のほか、ポール・コリア―教授、ヒュー・ウィッタカー教授との懇談に絞り、その概要を報告します。
■コリン・メイヤー教授
ビジネスが問題解決から利益を得る場合、それを政府が支援することは公共的な利益になる。そうすると当然連携が不可欠で、特に、社会課題の解決に取り組む場合には企業間や公的機関、政府との連携が不可欠である。
| 【専門分野】 | 経営学 |
| 【所属先】 | Saïd Business SchoolおよびBlavatnik School of Government |
| 【主な著書】 |
『Prosperity : Better Business Makes the Greater Good』(2018。邦題『株式会社規範のコペルニクス的転回』)、 |
■ポール・コリアー教授
企業はその性質上、持続可能であることを求めている。そうだとすれば、ビジネスが社会に提供できるものは大きいはずで、社会的な目的意識を持ったビジネスには大きなチャンスがあるといえる。そして企業には「啓蒙された自己利益(enlightened self-interest)」という長期的な思考が必要である。
例えば地域間格差や人口動態の問題があるが、イノベーションを起こすには若者が必要であるし、若者がいなければ収益性の高いビジネスを維持することはできない。若者が未来に希望を抱くためにはビジネスが信頼できるものでなければならず、それには持続可能性が不可欠だ。そしてそれは企業が社会に対して負っている責任である。
| 【専門分野】 | 経済学、公共政策学 |
| 【所属先】 | Blavatnik School of Government |
| 【主な著書】 |
『Greed is Dead : Politics After Individualism』(共著、2021。邦題『強欲資本主義は死んだ:個人主義からコミュニティの時代へ』)、 |
■ヒュー・ウィッタカー教授
日本にはいま、市場主義的資本主義、ステーク・ホルダー資本主義、国家主義的資本主義という3つの異なるベクトルの資本主義が存在しているといえる。今後、さまざまな安全保障の観点に基づく政策が行われることで国家主義的資本主義の方向が強まる可能性を懸念している。加えて、いまの市場主義的資本主義に偏りすぎている経済への危機感もある。3つのバランスをとることで、次の次元の資本主義へ発展できるのではないか。
異なるベクトルのものが衝突すると摩擦が生じるが、その摩擦を健全なものにして摩擦から新しいものを生み出す必要がある。そのためには、国と企業との対話、国と社会(経団連など個別企業ではないレベル)との対話が不可欠である。日本人は、矛盾するものを白黒つけずにバランスをとるということが得意で、そこが素晴らしいところだと感じている。
| 【専門分野】 | 日本経済ビジネス |
| 【所属先】 | Nissan Institute of Japanese Studies |
| 【主な著書】 |
『Compressed Development: Time and Timing in Economic and Social Development』(共著、2020)、 |
◇
3名に共通して、英米の企業が短期的な利益目標へ過度に焦点を当てていることへの問題意識を強く述べていました。今回の訪問では、企業が長期的な視点を持つ必要性や企業が社会課題の解決に取り組む必要性について意見交換することができました。来日が見込まれる教授もおられるため、当研究プロジェクトとして今後の連携を模索していきます。
※ 今回の訪問は、オックスフォード大学日本事務所 アリソン・ビール代表より多大なお力添えを頂戴して実現できましたこと、この場を借りて感謝申しあげます。