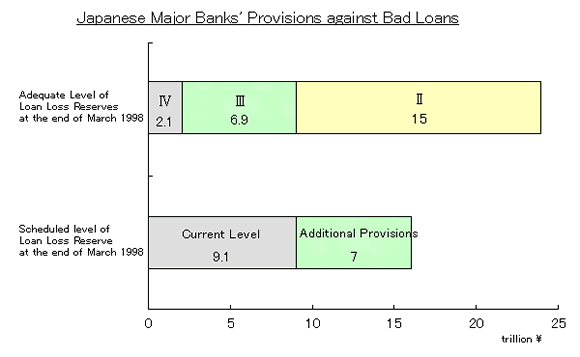「日本における金融システム改革の成果」
1998.3.5.
21世紀政策研究所
鹿野嘉昭
はじめに
21世紀政策研究所の鹿野でございます。私のほうからは、金融機関における不良債権の状況、不良債権処理に向けた環境整備のあり方などを中心として日本の金融システム改革の動きについてお話しさせていただきます。
1. 不良債権は一体いくらあるのか
まず最初は、日本の金融機関が現在抱えている不良債権の大きさです。これまで都市銀行などでは、アメリカのSEC基準などを参考にしつつ設けた独自の基準(日本基準と呼ばれます)にしたがって不良債権額を公表してきました。お手許の資料の2枚目をご覧ください。この資料は日本基準による銀行の不良債権額を取り纏めたものです。銀行の不良債権額は1997年9月末現在、合計22兆円となっています。このほか税務当局の認定を受けて経営支援を行っている貸出金が3兆円あり、これを合わせると不良債権総額は25兆円、貸出残高の3.8%に達しています。
これに対し、証券アナリストなどからは、公表不良債権額は実態を正確に反映していないという批判が投げかけられていました。というのも、日本基準の場合、3枚目の表2のとおりSEC基準と比較すると不良債権の認定基準が緩やかで、(1)利息の支払いが3ヵ月以上滞っている貸出金、および(2)変更後の貸出金利が公定歩合水準を上回っている貸出金については、これまでの間、不良債権から除外されてきたからです。したがって、アナリストの多くは、日本の銀行が抱えている不良債権額は公表金額の2〜3倍、貸出残高の10%程度にものぼるのではないかという見方をとるとともに、日本の銀行経営や情報開示姿勢に対する不信感を募らせていました。
こうした状況下、都市銀行などでは、投資家からの信頼回復を狙いとして本年3月期決算からSEC基準に合わせて不良債権金額を公表することを決定しました。したがって、今年の6月から日本の銀行による不良債権額の開示はアメリカの銀行とほぼ遜色のないものとなる予定です。ところで大蔵省では去る1月12日、銀行が試行的に実施した資産の自己査定の集計結果を公表しました。4枚目の表3がそれでございます。この表によりますと、回収に重大な懸念のある「III分類」および回収不可能を意味する「IV分類」に査定されたいわゆる分類債権は合計11兆円、これに回収に注意を要する「II分類」債権65兆円まで含めると77兆円にも達しています。また、11兆円という分類債権額と25兆円にのぼる公表不良債権額との隔たりは、「II分類」債権の約2割は実質的に不良債権化していることを示唆しています。
2. 金融機関の倒産はありうるか
それでは、77兆円という不良債権金額は日本の銀行にとって負担が重すぎるといえるのでしょうか。この問題を検討するに際しては、次の3点に留意する必要があります。第1は、今回の不良債権額は銀行検査基準という慎重性の原則に基づく資産分類査定の結果であり、潜在的な貸し倒れリスクをすべて含む最もカバレッジの高い計数であるという点です。第2は、そうした要注意債権をも含めて不良債権残高を公表した例は、今回の日本のケースを除けばほとんどないという点です。第3に、不良債権残高の多寡を判断するに際しては、将来の損失発生に備えて積み立てられている貸倒引当金を控除した要償却額が重要となるということです。
資料5枚目の表4をご覧ください。これは、アメリカおよび日本における貸倒引当金の積み立て基準を示したものです。両国の銀行とも、この基準にしたがって不良化した貸出債権に対する引き当てを行っています。例えば都市銀行、長期信用銀行および信託銀行の場合、III・IV分類に分類された債権は約9兆円あります。これに対し9兆円の特定引当金が積み立てられており、III・IV分類資産についてはほぼ全額引き当てられていることが分かります。したがって、残された問題はII分類債権45兆円に対し、どれだけの引き当てを行うのが適切かということです。先に述べた公表不良債権額とIII・IV分類資産額との差額に相当する10兆円については全額引き当て、残りの35兆円については15%の引き当てを行うと仮定して今後必要となる引当金額を試算すると、15兆円程度という結果がえられます。
都市銀行等ではこの3月期決算において7兆円程度の引き当てを行う予定にあるほか、年間の業務純益は3.6兆円程度にのぼっているため、日本の銀行を長年にわたって悩ませてきた不良債権処理問題にも漸く展望が開けつつあるということができます。一方、地域銀行の場合、同様の試算を行うと、不良債権処理のためにはあと4年程度の時間を要することが分かります。いうまでもなく、ここでの試算は不良債権問題の現状把握を目的とした腰だめ的なものであり、地域銀行のすべてが不良債権問題に悩まされていることを示唆しているわけではありません。
しかしながら、預金者心理が動揺し、質への逃避が静かに進行しているだけに、今後個々の銀行における経営内容の悪化を伝える情報が流れると、問題銀行においては預金の大幅な流出から資金繰りに窮し、営業停止に追い込まれるという事態が発生する可能性もあります。万が一、そういった事態に至った場合、銀行の破綻が局所的な問題にとどまるか、日本経済を揺るがすような金融危機を招来するかは預金者心理に大きく依存しているため、銀行預金の安全性に対する預金者の信認を確固たるものにしておく必要があります。さきほど宮沢元総理からお話がありました金融システム安定化対策は、こうした観点から導入されたものであり、その結果、銀行破綻に伴う悪影響は、あったとしても最小限の範囲にとどまるであろうと確信しています。
3. 早期是正措置の導入の意義
次に、日本における早期是正措置導入の意義と効果について説明させていただきます。資料5枚目の表4をご覧ください。これが、日本の銀行に対して本年4月から導入が予定されている早期是正措置の概要であり、基本的には約5年前にアメリカで設定された措置を踏襲しております。残念ながら、各種措置の発動に関しては1年間先送りされました。このため、早期是正措置に関する内外投資家からの評判は余り芳しくありません。しかし、私としては、この措置の導入は日本の銀行監督史上非常に意義深いものであることを皆さんに強調することができればと考えております。早期是正措置の導入は、不良債権情報の一段の開示と相俟って、当局に対しては従来の裁量的な銀行監督政策の放棄とルールに基づく透明性の高い銀行行政への移行を求めるほか、銀行経営者に対しても市場との対話を意識した経営への転換を促すからです。
一般論として、企業経営の善し悪しは投資家により判断され、その結果は各企業の株価にビビッドに反映します。しかし、日本の銀行の場合、これまでの間、大蔵省が銀行法に定められた監督権限に基づき実質的に銀行経営を監視するという役割を果たしてきました。店舗の新設・廃止、新商品の販売、不良債権の償却など銀行経営の根幹にかかわる事項に関しては、いずれも大蔵省による事前承認が必要とされていました。そうしたなかで、銀行行政も護送船団方式と称されるようにきわめて保護色の強いものになったと思われます。
このような保護行政は、銀行にとっても都合に良いものでした。大蔵省の指導を遵守している限り、競合相手に抜かれることは決してないというように「順番が仕切られた競争」のなかに安住することができたからです。また、そうした環境のなかにあっては、いくら革新的な商品を開発したとしても当然得られるべき創業者利潤も平等に分配することを求められるというのが一般的でした。その結果、銀行経営者においては自己規律意識や革新を起こそうとする意欲が減退し、大蔵省頼りの経営となり、それがまた大蔵省の権限を高めるというかたちで作用してきました。これらが全体として、現在の「責任の所在および方向感覚がはっきりしない」という銀行経営を醸成してきたのではないかと考えております。
金融のグローバル化が進んだ今日の世界にあって、そうした事態が好ましくないことは明らかです。しかし、「仕切られた競争」は銀行、大蔵省双方にとって座りごこちの良いものであったため、誰もが問題があることを承知しつつも、これを積極的に破壊しようとする動きはほとんどみられませんでした。早期是正措置の導入は、この強固な安定均衡を破壊し、大蔵省に対してはルールに基づく透明性の高い銀行行政への移行を、また銀行には自己責任の原則に基づく市場との対話を意識した経営への転換をそれぞれ求めているのです。換言すると、日本の銀行界も本年4月以降、革新的な意識に燃えた銀行は一歩前に出られるようになった一方、特色のない銀行は市場において容赦なく淘汰される世界に漸く突入することになったのです。
4. 早期是正措置は銀行破綻を促進するか
早期是正措置は、日本の銀行に対し自己資本比率の公表を求めています。これにSEC基準に準拠した不良債権残高に関する情報開示を合わせると、普通の預金者からみても「いい銀行」と「悪い銀行」が自然と炙り出され、そうしたなかで経営内容が大きく劣った銀行については市場から退出させようとする力が働きます。市場において退出すべきと判断された銀行は、公的資金の投入により預金者の保護を図ったうえで破綻することになります。問題は、破綻銀行と取引関係にあった企業の保護です。この点に関しても、今回の預金保険法の改正によって手当てされています。
すなわち、整理回収銀行の業務内容や調査権限が強化され、整理回収銀行はアメリカでいうとRTCとブリッジバンク両者の機能を併せ持った強固な銀行に改編されたのです。これまでは破綻銀行の処理に際しては借り手保護のため、正常債権を承継する銀行あるいは受け皿銀行を見出す必要があり、これが破綻銀行処理上大きな障害となっていました。しかし、これからは破綻銀行の債権はすべて整理回収銀行が引き継げるため、受け皿銀行の確保を意識することなく粛々と破綻銀行を処理できるようになったのです。換言すると、日本においても漸く破綻銀行を円滑に処理できる環境が整備され、今後、銀行破綻の増大にも十分対応できるようになったのです。
したがって本年7月以降、経営内容に問題のある銀行は厳しい試練の時代に突入すると思われます。効率性の劣る銀行が淘汰されるのは市場経済の大原則であり、日本の金融システムの効率化を達成するためにも、預金者および借り手保護措置を拡充のうえ破綻すべき銀行については躊躇することなく破綻させることが一段と重要になっているだけでなく、実際にも銀行の淘汰が大きく進むと思われます。
5. おわりに
今月の初め、約2年ぶりにスイス人の友人に会いました。彼は現在、投資銀行に勤務し、日本株の投資分析に従事しています。彼に日本の銀行株に関する投資方針を聞いたところ、「当分の間は見送りたい」という反応がありました。その根拠としては、次に3点が挙げられていました。第1に、不良債権の実態に関するディスクロージャーが十分でない。第2に、ROA、ROEの低さが示すように、収益性が極端に低い。第3に、銀行経営者の経営方針がみえない。残念ながら、現状まさにそのとおりであり、ここのいらっしゃる方々の多くもそうした見方に共感されると思っております。日本の銀行は上記3つの基準を満たすべく変わらなければならりません。
これまでの日本の銀行の行動から判断すると、それはかなり困難なことです。しかし、私としては、逆説的かもしれませんが、間もなく変わるであろうと確信しています。そうでなければ、日本国内における資産運用競争に敗れてしまうからです。本年4月からは外為法が自由化され、外資系金融機関の日本市場への参入が本格化するため、これまでのような「仕切られた競争」のなかに安住できる時代は終わったのです。預金にこだわり、魅力ある金融商品を提供できなければ1200兆円にのぼる個人金融資産を外資系の銀行や証券会社に奪われてしまう可能性が高まっています。
日本の製造業は円高という試練のなかで競争力を向上させてきました。製造業に遅れること25年、日本の銀行もそうした厳しい試練のなかに漸く放り込まれたのです。この試練をどれだけの銀行が生き残れるのか予断は許されませんが、公的資金に頼らずにここアメリカ市場において優先株を発行する動きがみられるなど、一歩先んじようとする革新的な動きの萌芽がやっと出始めるようになりました。今後、そうした動きが日本の銀行のなかへと広がっていくことを期待しつつ、これをもちまして私からの報告を終えさせていただきます。ご静聴ありがとうございました。
表1 Japanese Bank's Bad Debts Reached a Total of 22 trillion yen. But...
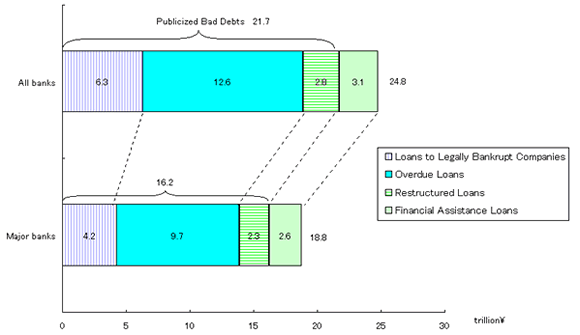
表2
To Respond to Requests for Forthright Disclosure, Japanese Banks Decided to Change the Definitions of Nonperforming Loans to be compatible with the US Standards from March This Year.
| Definitions | Data Disclosed | |||
| U.S.A. | Japan | |||
| Up to the end of September 1997 |
From the end of March 1998 |
|||
| Nonperforming Loans | Past Due for Three Months or More up to Six Months | O | X | O |
| Past Due for More than Six Months | O | O | O | |
| Restructured Loans | The Interest Rate Payable Was Reduced to a Level below the Official Discount Rate | O | X | O |
| The Interest Rate Payable Was Reduced to a Level above the Official Discount Rate | O | O | O | |
| Financial Assitance Loans Approved by the Taxation Authorities | O | O | O | |
| Composition of Classified Loans |
Each Bank's Self Assessment Criteria | X | O | ? |
表3 Recent Data Show that Total Classified Loans of Japanese Banks Amount to 77 Trillion Yen
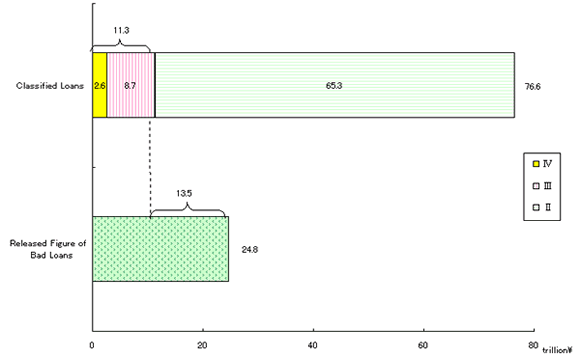
表4
Banks Make Provisions against Bad Loans According to Accounting Standards in General Use
| Accounting Standards for Making Provisions | |||
| U.S.A | Japan | ||
| Up to fiscal 1996 | From fiscal 1997 | ||
| Pass | Historical Probability |
0.3% | Historical Probability |
| Special Mention | |||
| Substandard | 15% | ||
| Doubtful | 50% | Amount of Possible losses |
Amount of Possible Losses |
| Loss | 100% | 100% | 100% |
表5