4. 厚生年金民営化に関する我々の提案
1. 厚生年金民営化がなぜ必要なのか
年金の財政方式には、積立方式と賦課方式がある。積立方式とは、引退世代となったときに受け取る年金の原資を現役時代に自分で積み立てる仕組みのことをいう。これに対し、引退世代の受け取る年金をその時の現役世代から徴収する保険料でまかなう仕組みのことを賦課方式という。日本の公的年金制度は修正積立方式と呼ばれる仕組みに基づき設計、運営されている。修正積立方式とは、引退世代への給付については基本的にその時の現役世代から徴収した保険料でまかないつつも、年金制度が成熟化(引退世代の人口の比率が高まったのち高位安定すること)していないときに徴収する保険料の中の一部を積み立てておき、年金制度が成熟化したときに、引退世代に対する給付の一部をその積立金の運用収入でまかなう仕組みである。積立金は、年金制度が成熟化したときの保険料の高騰を防ぐバッファーの役割をもっている。修正積立方式では、積立金というバッファーは存在するにせよ、現役世代に対して引退世代の人数が増えれば増えるほど保険料は上昇する。逆に保険料の高騰を抑制するには、年金給付をカットする以外に方法はない。現在は予想を上回るペースで少子・高齢化が進んでいるため、保険料の引き上げやtのカットといった年金改革案が検討されているのだ。保険料の引き上げや給付のカットがおこなわれれば、保険料拠出と年金給付のバランスについて世代間の不公平が生じる。この仕組みで公的年金制度を運営する場合、少子・高齢化という制御不可能な要因によって保険料の引き上げや給付のカットがおこなわれる可能性があること、その結果拠出と給付のバランスについて世代間の不公平が生じること、の2点について国民的覚悟と合意が必要とされる。
日本の公的年金制度は2階建ての仕組みである。1階部分とは定額の基礎年金部分で、2階部分とは就業期間中の所得に応じて金額が決まる報酬比例部分である。つまり、最低限の生活の保障に加えて、生活をより豊かにするためのプラスアルファの給付がおこなわれていると考えてよい。
基礎年金部分に関しては、退職後の生活の最低保障であり、これはどんなことがあっても国民全体で支えるべきであるという国民的覚悟と合意は得られるであろう。またその性格上、確実な給付を国民全体からの確実な拠出によりまかなうという観点からすると、基礎年金部分については全額消費税方式による賦課方式にするべきと考えられる。消費税を財源とすれば、インフレによる目減りも少なく、その時の物価水準等を反映した給付をおこないやすい。
報酬比例部分についてこうした国民的覚悟と合意は得られるだろうか。報酬比例部分は、より豊かな老後の生活を目的として、就業中の所得に応じて支給されるプラスアルファの部分である。公的年金制度について、拠出と給付のバランスについての不満が高まってきているのは、実はこの報酬比例部分についてのことなのである。報酬比例部分に関しては、どんなことがあってもその時の現役世代で支えるべきであるという国民的覚悟と合意は得られていないとみるのがむしろ自然であろう。これまでの間、まさかここまで少子・高齢化が進むなどとは誰も思っていなかったので、報酬比例部分を一体誰が負担すべきなのかについて、真剣に議論されることはほとんどなかった。しかし、少子・高齢化が急速に進むに至って、拠出と給付のバランスについて不満が高まってきており、実はどんなに負担が増そうが引退世代の報酬比例部分まで面倒をみるという国民的覚悟や合意ができていないことが明らかになってきたのだ。我々は、あらためてこうした国民的覚悟と合意が確認されない限りにおいては、報酬比例部分については積立方式に移行するべきであると考える。その際、積立金の運用は多様な担い手からなる民間部門によっ・ぢこなわれることが望ましいという観点から、厚生年金は民営化されるべきであると考える。
2. 二重負担の問題
厚生年金の民営化に対する反論としてよく議論されるのが、いわゆる二重負担の問題である。厚生省では、この移行コストに関わる問題を「二重負担の問題」としてとらえ、「賦課方式から積立方式に切り替える場合に、切替時の現役世代が、自らの将来の年金に加えて、別途の形でその時の受給世代等の年金を負担しなければならなくなるという問題」と説明している。厚生省によれば、この二重負担は350〜380兆にもおよぶという。
しかしここで留意しなければならないのは、二重負担の問題は積立方式に移行することによって発生する問=題ではない、ということである。賦課方式(あるいは修正積立方式)の年金制度においては、現役世代は保険料を払った時点で将来の年金受給権が発生するが、その負担は将来の現役世代に求めることとし、いわば負担を先送りしている。積立方式への移行の際には、それを目に見えるかたちにして、償却が求められるというにすぎないのだ。これは、ちょうど2000年度から適用される会計基準の変更において、企業が退職給付債務を発生基準で認識し、これまでオフバランス化していた企業年金の積立不足をオンバランス化するとともに、これを償却することが求められているのと同じことだ。
真に必要なのは、将来にわたる国民の負担と受益の関係について明らかにし、二重負担の償却原資をどのようにファイナンスするかを議論することである。未積立債務のファイナンスの方法については、次節の厚生年金民営化の具体的な手法の中で説明する。
- (1)過去期間の保険料に対応した未積立債務をファイナンスする。
- (2)(1)でファイナンスされた未積立債務と現存の積立金の合計を現役世代と引退世代に分配する。
- (3)現役世代は、新しく設ける個人別勘定、これまで払ってきた保険料に対応した分配金を受け取る一方、現時点で既に引退している世代に対しては、現行どおりの年金を給付する。
- (4)役世代が受け取った分配金は強制加入の企業年金等に移行する。
(1)にある未積立債務のファイナンスは、次の手法でおこなう。
- 報酬比例部分の年金給付債務を、現時点で既に引退している世代に対するこれからの給付の部分と現役世代がこれまで払ってきた保険料の積立金の部分に大別する。
- 現時点で既に引退している世代へのこれからの給付については、各年度ごとの財政負担とする。
- 現役世代への積立金の分配については、積立金および60歳時点で現金化できる交付国債でファイナンスすることとする。
- 財政負担および交付国債償還の財源のうち、200兆円については、永久国債の発行でまかなう。
3.の交付国債の発行は、いわば将来の年金受給権を国が保証する約束手形を発行するのに等しい。4.の永久国債の発行は、移行コストの一部を遠い将来世代にまでわたって薄く広く負担させようという考え方に基づく措置である。
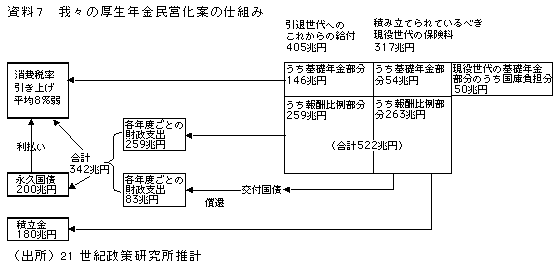
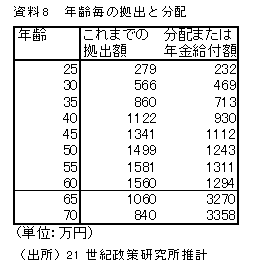 資料8は、これまでの拠出額に応じて現役世代への分配金を年齢ごとに試算したものである。(ただし、引退世代は年金給付)。例えば、50歳の人は、積み立てられているべきこれまでの保険料が1499万円であるのに対し、基礎年金相当部分を除く1243万円の分配金が受け取れるという計算になる。
資料8は、これまでの拠出額に応じて現役世代への分配金を年齢ごとに試算したものである。(ただし、引退世代は年金給付)。例えば、50歳の人は、積み立てられているべきこれまでの保険料が1499万円であるのに対し、基礎年金相当部分を除く1243万円の分配金が受け取れるという計算になる。
本来自分たちの持ち分であるべき年金資産が、政府の勘定ではなく個人の勘定に明示的に計上されれば、将来に対する漠然とした不安からいたずらに支出を抑える必要はなくなる。我々は将来にわたる生活設計の中で、それぞれの裁量で投資や消費ができるようになるのだ。資料9は、国家財政への影響を示したものである。例えば、2004年度を例にとってみよう。基礎年金の財源が18.1兆円必要であり、これは消費税率に直すと4.5%の負担となる。報酬比例部分については、現時点で既き上げに相当する財政負担が必要なわけだ。惹闔龠皷齦就旺昭齦霈錫庄鹿眈鹿齦霈鹿肬銓徐ぢ我々の提案による国家財政への影響は、平均してだいたい消費税率換算 8%弱となる。
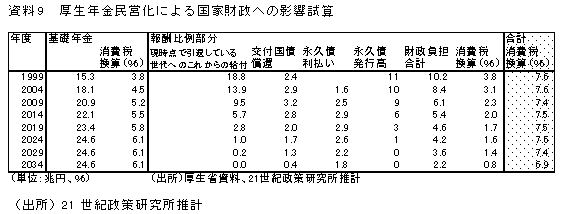
1. ここでは即時に消費税率を8%引き上げるとしているが、その他の消費税率引き上げパターンも、参考資料として巻末に掲載した。
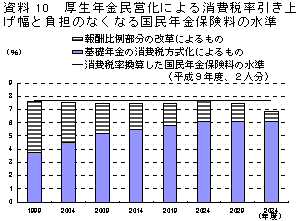 一方、基礎年金部分を消費税方式へと変更することより、国民年金保険料(および基礎年金部分の保険料)負担がなくなることを忘れてはならない。1999年度の1世帯当たりの国民年金保険料(2人分)は月額26600円であり、この負担がなくなるということは、一般国民による年金保険料負担は消費税率に換算して7.8%程度減少することになる。つまり、2人分の国民年金保険料を支払っている標準的な世帯では、ネットの負担増はわずかにとどまる。この点から考えれば、この程度の財政負担を求めることはそれほど非現実的なこととは思えない。
一方、基礎年金部分を消費税方式へと変更することより、国民年金保険料(および基礎年金部分の保険料)負担がなくなることを忘れてはならない。1999年度の1世帯当たりの国民年金保険料(2人分)は月額26600円であり、この負担がなくなるということは、一般国民による年金保険料負担は消費税率に換算して7.8%程度減少することになる。つまり、2人分の国民年金保険料を支払っている標準的な世帯では、ネットの負担増はわずかにとどまる。この点から考えれば、この程度の財政負担を求めることはそれほど非現実的なこととは思えない。
4. 国債発行によるクラウディングアウトの懸念について
昨年7月に我々がこの厚生年金民営化案を発表したあと、この案における国債の大量発行がクラウディングアウトを引き起こすことを懸念する意見が聞かれた。しかし我々は、国債発行によっておこなわれるのは、いわばもともと存在する隠れ債務のオンバランス化にすぎず、金利の上昇につながるようなIS曲線の移動をともなうものではない、と考えている。公的年金の未積立債務の存在は、既に国債の価格のなかに織り込まれているのだ。
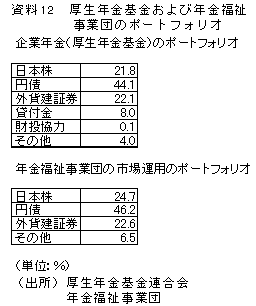 ここで、国債の需給についてくわしく見てみよう。我々の年金改革案では、350兆円の未積立債務は、交付国債83兆円、永久国債200兆円の発行のほか、残りの67兆円分は消費税率の引き上げにより一般財政で対応する。
ここで、国債の需給についてくわしく見てみよう。我々の年金改革案では、350兆円の未積立債務は、交付国債83兆円、永久国債200兆円の発行のほか、残りの67兆円分は消費税率の引き上げにより一般財政で対応する。
国債を発行する分だけ国債の供給は増えるが、あらたに登場する現役世代の個人別勘定における運用により需要も増える。
資料13は、各年度における国債発行額と、現役世代の個人別勘定における国債、株式への投資額の見通しである。改革時に、現役世代の個人別勘定に263兆円の積立金が登場することとなるが、現下の企業年金のポートフォリオから考えて、このうち約116兆円が円債、約57兆円が日本株に投資されると見込まれる。その後、積立金の増加に伴って円債(2034年までに約209兆円)や日本株(同じく約104兆)への投資が見込まれる。
一方、99年度末現在の年金積立金180兆円は、2現下の年金積立金運用の配分から考えて、財投に約131兆円、住宅融資に約14兆円、市場運用に約34兆円投資されており、このうち、円債に約16兆円、日本株に約8.5兆円投資されていると推計される。
以上から、ネット(個人別勘定の積立金による投資額から現在の年金積立金の投資額を差し引いたもの)でみると、改革時に円債は約6兆円の需要超過、2034年までに約15.3兆円の需要超過が見込まれる。国債の需給については、むしろ国債価格の上昇(金利の低下)要因になる。
また、日本株は改革時に約49兆円、2034年までに約152兆円の需要超過が見込まれる。現在解消圧力にさらされる株式は数十兆円規模といわれていることから、現役世代の個人別勘定による投資は、株式持ち合い解消の受け皿となる可能性が期待できる。
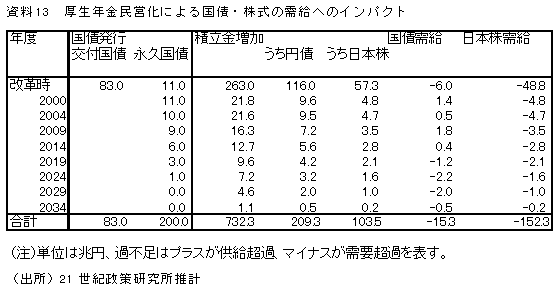
このように、公的年金の未積立債務を国債発行で穴埋めしても、理論的には国債価格の下落(金利の上昇)は起こらず、クライディングアウトも起きない。政府の隠れ債務の顕在化を通じて生じるのは、資産・負債の移転にすぎないのだ。
2. あらたな年金積立金の運用ポートフォリオが現下の企業年金のポートフォリオと近いものになるかどうかは検討を要する。例えば、米国では、特に確定拠出型年金導入当初は、その運用ポートフォリオが確定給付型年金のそれよりもリスク回避的だったことが知られている。