3. 確定拠出型年金導入についての我々の見解
1. 確定給付型年金・確定拠出型年金のメリット・デメリット
確定給付型年金は加入した期間や賃金水準などに基づいてあらかじめ年金給付額が決まっている仕組みで、確定拠出型年金は拠出した掛金額とその運用収益に基づいて年金給付額が決まる仕組みである。以下では、確定給付型年金・確定拠出型年金それぞれのメリット・デメリットを整理する。
1. 確定給付型年金
(メリット)
- 給付額が確定している(従業員が運用リスクを負わない)
- 投資規模が大きく、運用リスクを分散しやすい
- 従業員を企業に定着させるインセンティブとなる
- 従業員教育が不要
(デメリット)
- ポータビリティーがない
- 従業員ごとの年金原資が明確でない
- 企業が運用リスクを負う
- 会計上確定給付債務として認識される
- 煩雑な数理計算や報告義務がある
2. 確定拠出型年金
(メリット)
- ポータビリティーがある
- 企業が運用リスクを負わない
- 従業員が運用方法を選択可能
- 従業員ごとの年金原資が明確
- 会計上確定給付債務として認識されない
(デメリット)
- 給付額が不確定(従業員が運用リスクを負う)
- 投資規模が小さくリスク分散がしにくい
2. 米国における確定拠出型年金の急成長(401Kプランを中心に)
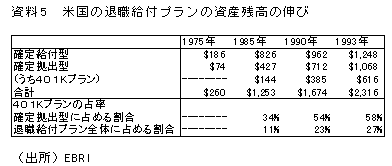 米国では、1974年に世界で初めての包括的な企業年金法であるERISA法(被用者退職所得保障法)が制定された。ERISA法の主な内容は、企業年金財政のディスクロージャーに関する規定、受給権保護に関する規定、積立基準に関する規定、受託者責任およびプルーデントマンルールに関する規定、制度終了保険およびPBGC(年金給付保証公庫)に関する規定、個人所得勘定(IRA)の導入、などである。 ERISA法が制定以降、とくに1980年に401Kプランが施行されてから、確定拠出型年金は急速な発展をとげた。かつて資産規模の小さかった確定拠出型年金は確定給付型年金を上回る成長を示し、現在両者の資産残高はほぼ同じになっている。とくに確定拠出型年金のなかでも401Kプランの伸びが著しく、1985年から93年の間で年率20%近い伸びを示した。
米国では、1974年に世界で初めての包括的な企業年金法であるERISA法(被用者退職所得保障法)が制定された。ERISA法の主な内容は、企業年金財政のディスクロージャーに関する規定、受給権保護に関する規定、積立基準に関する規定、受託者責任およびプルーデントマンルールに関する規定、制度終了保険およびPBGC(年金給付保証公庫)に関する規定、個人所得勘定(IRA)の導入、などである。 ERISA法が制定以降、とくに1980年に401Kプランが施行されてから、確定拠出型年金は急速な発展をとげた。かつて資産規模の小さかった確定拠出型年金は確定給付型年金を上回る成長を示し、現在両者の資産残高はほぼ同じになっている。とくに確定拠出型年金のなかでも401Kプランの伸びが著しく、1985年から93年の間で年率20%近い伸びを示した。
ERISA以降に確定拠出型年金、とくに401Kプランが急成長した理由には、次のようなことが考えられる。(1)確定給付型年金に求められる制度維持コスト(制度終了保険の保険料など)が上昇したほか、煩雑な数理計算や報告義務が生じたこと、(2)80〜90年代にかけて、競争的なビジネス環境を背景に労働市場の流動化が進み、労使双方からポータビリティーのある確定拠出型年金が選好されたこと、(3)80年代後半を除けば、株式市場をはじめ運用環境がおおむね好調に推移したこと、などがあげられよう。
ただここで留意すべきなのは、この時期米国では確定給付型年金から確定拠出型年金へシフトした、とは単純にいえない点である。確定給付型年金の加入者数はほぼ横ばいであり、一方で急増している確定拠出型年金の加入者のほぼ半数が確定給付型年金にも加入している。このことは、上記の(1)や(2)のような動機により確定給付型年金を確定拠出型年金に変更、既に確定給付型年金を導入している企業があらたに若く優秀な人材を集めかつ彼らに労働インセンティブを与えるために追加的に確定拠出型年金を導入、新しく生まれた企業などでコストが安くかつ流動化した労働力を獲得しやすい確定拠出型年金を導入、といった様々な企業行動の結果と推察される。
このように米国において確定給付型年金に加えて確定拠出型年金がいわば追加的に普及していった背景として、公的年金の水準の低さと貯蓄水準の低さを指摘しておかねばならない。米国の公的年金制度は、OASDI(社会保障年金)および公務員年金である。前者には約1億4700万人、後者には約2400万人が加入している。OASDIの給付水準は月額約765ドルであり、必要最低限の保障をおこなうにとどまっている。企業年金がそれを補完し、まさしく公的年金と企業年金をあわせて従前所得の一定割合をカバーする設計になっている。したがって、401Kプランのような思い切った課税繰り延べ措置を導入して老後資金の貯蓄を促すことには大きな意味があった。雇用主や従業員の立場からみても、企業年金を充実させることは、従業員の老後生活を保障するという意味で、非常に重要な課題であった。また、一般に貯蓄の増強は資本ストックの増大を通じて経済の成長力を高めるが、米国ではいかにして貯蓄水準を高めるかが経済政策上の重要な課題であった。企業年金に税制優遇措置を与え、年金資産の蓄積を促すことには、マクロ経済政策の観点からも大きな意味があったのだ。
米国の確定拠出型年金は、雇用の流動化を通じて労働市場の活性化を促したほか、mutual fund等経由で個人の資金が大量に流入したことを通じて資本市場の活性化を促したことが指摘されることが多い。しかし、資本市場に個人の資金があらたに流入した背景には、低水準の公的年金と貯蓄という米国特有の要因があったことを踏まえておく必要があると思われる。
3. 日本における確定拠出型年金導入の意味
先に述べたとおり、日本において企業拠出型の確定拠出型年金は現行の厚生年金基金や適格退職年金からの移行・上乗せ・新設などの導入形態が想定されている。つまり、確定拠出型年金は退職金制度と密接に関連することとなる。
退職金制度に関しては、2000年度より会計基準が変更され、退職給付債務を発生基準で厳格に認識しオンバランスすることとなった。企業はこれまでオフバランス化していた企業年金の積立不足をオンバランス化するとともに、積立不足を最長15年以内に償却することが求められることとなる。積立不足は一部の試算では上場企業ベースで60〜80兆円あるともいわれ、企業財務を圧迫する大きな要因として懸念されている。この対応策として、退職給付債務として認識されない確定拠出型年金の導入が期待されているのもそのためである。
しかしながら、確定拠出型年金が導入されれば積立不足が煙のように消えるわけでは決してない。退職金原資が確定拠出型年金の仕組みで積み立てられば、運用リスクの担い手は企業から従業員に移る。このことは、現下の運用環境下においては実質的な退職金の水準の引き下げにつながる可能性が高い。つまり、積立不足の問題を給付水準の切り下げによって解決するのと同じことだ。退職金の水準の引き下げは労使の合意を前提とするが、その交渉は難航すると思われる。
終身雇用や年功賃金日本的雇用慣行は、日本の高度経済成長を支えたといわれるシステムで、とくに企業の側では、できるだけ維持していこうとする考え方が多い。しかし一方で、一部の企業では、厳しい経営環境のなか労働力を適材適所に配置することが重要な経営課題となってきている。また、従業員側からみると、ライフスタイルが多様化し、自分の個性と能力が最大限生かせる職場を求める考え方が台頭してきている。このような状況の変化を背景に、雇用の流動化に柔軟に対応できる社会的な仕組みが求められてきている。労使の合意というハードルを乗り越え、確定拠出型年金が導入されれば、それは雇用の流動化を促す第一歩となり、労働市場の活性化に一定の役割を果たすことになると期待できる。ちなみに、退職金前払い制度として1998年度に導入された松下電器の「全額給与支払い型社員」制度では、1998年度入社者の約40%がこの制度を選ぶ意思表示をしたといわれている。
また、労使の合意を比較的実現しやすい仕組みとして、ハイブリッド年金の導入が議論されている。ハイブリッド年金の例として、確定給付型年金と確定拠出型年金の折衷的なもので、(1)掛金は事業主のみが拠出し、資産運用は従来どおり企業がおこなう、(2)給付額は、運用成果により決定されるが、企業が運用の最低保障をおこなう、(3)個人の持ち分については計算上の管理をおこなう、というものがある。これは、ポータビリティーが付与しやすいこと、従業員にとって一定の利回りが保証されること、企業にとってオンバランス化が必要な年金債務が小さくてすむこと、などのメリットがある。ただし、従業員が運用方法を決定できないという面では不十分である。
ハイブリッド年金は、のちに確定拠出型年金(個人拠出型も含む)への移行が可能である。米国では、確定給付型年金を採用していた企業年金が、まず労使の合意を形成しやすいハイブリッド型年金に移行した例も多い。労働市場の活性化という観点からは、こうした実現可能性の高い選択肢を用意しておくことも有効と考えられる。
日本で確定拠出型年金が導入された場合、それは資本市場の活性化につながるだろうか。確定拠出型年金では、個人が自分の年金資産の運用方法を選択する。個人が自らの老後を豊かなものにするため一定のリスクをとって投資をおこなうことは、多様な個人投資家を育成することにつながるうえ、資本市場の奥行きを広げることになる。このことはまた、各人が自己のとりうるリスクと期待するリターンを見きわめることを通じて長期的な経済社会の安定性が担保されるという、新しい経済システムへの転換への契機となろう。
しかし、企業拠出型の確定拠出型年金においては、厚生年金基金、適格退職年金(いわゆる3階部分)から確定拠出型年金への移行が想定されている。3階部分はもともと積立方式で運営されており、運用リスクの担い手が企業から従業員にかわるだけで、資本市場にあらたな資金が流入するわけではない。この点では、米国で見られたような資本市場の劇的な変化はあまり期待できない。
既存の確定給付型年金への上乗せ、あるいは確定拠出型年金の新設は、日本の公的年金と貯蓄の水準の高さを考えると、米国ほどの増加は期待できそうにない。日本の厚生年金では、標準的な世帯の月額で、基礎年金で約13万円、報酬比例部分で約10.1万円の合計約23.1万円の給付がある。企業年金で追加的な年金を準備する必要性は米国ほど高くない。また現在、日本の個人金融資産は98年末現在で約1260兆円にのぼり、貯蓄水準は非常に高いといわれる。したがって、この上追加的に貯蓄を増やすインセンティブは米国ほど高くないと考えられる。このことは、大蔵省などが確定拠出型年金への税制優遇措置に難色を示す1つの理由ともなっている。
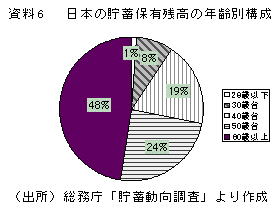 以上から我々は、現在想定されている確定拠出型年金の導入について、労働市場の活性化には一定の役割を果たしうるが、資本市場の活性化には米国で見られたほどの効果はないと考えている。我々は、資本市場の活性化のためには、現在修正積立方式で運営されている公的年金の報酬比例部分を積立方式に移行し民営化することこそが必要だと主張したい。
以上から我々は、現在想定されている確定拠出型年金の導入について、労働市場の活性化には一定の役割を果たしうるが、資本市場の活性化には米国で見られたほどの効果はないと考えている。我々は、資本市場の活性化のためには、現在修正積立方式で運営されている公的年金の報酬比例部分を積立方式に移行し民営化することこそが必要だと主張したい。
日本の個人金融資産は98年末現在で約1260兆円にのぼるが、その半分近くは高齢者が保有している。高齢者の保有する金融資産はその性格上それほどリスクをとるインセンティブがない。リスクとリターンを厳しく見きわめなければならないのは、老後を豊かなものにする目的で運用される現役世代の金融資産だ。公的年金の積立方式への移行と民営化によってあらたな性格をもつ個人金融資産が登場すれば、投資行動の奥行きが広がり、資本市場の活性化につながると期待できる。そのうえで、確定拠出型年金がその民営化の受け皿の一つとなることが望ましい。