2. 年金改革をめぐる最近の議論
1. 公的年金制度改革についての最近の議論
公的年金は5年ごとに給付と負担の将来見通しを見直し(財政再計算)、あわせて制度改正をおこなっている。現在、99年公的年金制度改正に向けた議論が進められている。公的年金制度は、少子・高齢化の進展、経済成長率の鈍化、女性の社会進出や高齢者の生活意識の変化等、状況の変化に対応していかなければならない。なかでも、現役世代からは支払った保険料に見合う年金給付が受けられるだろうかという不信が、また年金受給者からは今後とも予定通りの年金が受け取れるのだろうかという不安が高まってきており、信頼できる持続可能な年金制度の確立が強く求められている。
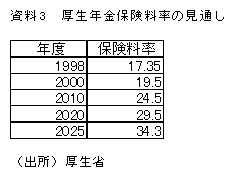 97年はじめに、従来の推計よりも少子・高齢化が加速すると見込んだ国立社会保障・人口問題研究所の新しい人口推計に対応する厚生年金の財政見通しが発表され、現行17.35%の保険料率は2025年には34.3%まで引き上げなければならないとの見通しが示された。94年に厚生省が実施した有識者調査では、保険料負担の上限は30%程度とする回答が最も多かったことなどから、保険料の負担と年金給付のあり方についてもう一度見直すことが避けられない情勢となった。年金審議会では99年公的年金制度改正に向けた検討を97年5月27日より開始し、同年12月5日に「論点整理」をとりまとめた。また同じ12月5日に厚生省より「5つの選択肢」が提示され、保険料負担の引き上げと年金給付の削減の組み合わせ、あるいは厚生年金の報酬比例部分の民営化、といった改革案が示された。その後議論が重ねられ、98年10月9日に年金審議会の意見書がとりまとめられ、同年10月28日に厚生省年金局の公的年金制度改正案が発表された。ここでは3つの案が提示されたが、いずれも基本的に現行制度の枠組を維持したうえで保険料負担の引き上げと年金給付の削減をおこなうもので、賃金スライドの凍結、60歳台後半の在職老齢年金の導入、総報酬制(ボーナスも含めた年収をベースとした保険料徴収)の導入、などが盛り込まれている。
97年はじめに、従来の推計よりも少子・高齢化が加速すると見込んだ国立社会保障・人口問題研究所の新しい人口推計に対応する厚生年金の財政見通しが発表され、現行17.35%の保険料率は2025年には34.3%まで引き上げなければならないとの見通しが示された。94年に厚生省が実施した有識者調査では、保険料負担の上限は30%程度とする回答が最も多かったことなどから、保険料の負担と年金給付のあり方についてもう一度見直すことが避けられない情勢となった。年金審議会では99年公的年金制度改正に向けた検討を97年5月27日より開始し、同年12月5日に「論点整理」をとりまとめた。また同じ12月5日に厚生省より「5つの選択肢」が提示され、保険料負担の引き上げと年金給付の削減の組み合わせ、あるいは厚生年金の報酬比例部分の民営化、といった改革案が示された。その後議論が重ねられ、98年10月9日に年金審議会の意見書がとりまとめられ、同年10月28日に厚生省年金局の公的年金制度改正案が発表された。ここでは3つの案が提示されたが、いずれも基本的に現行制度の枠組を維持したうえで保険料負担の引き上げと年金給付の削減をおこなうもので、賃金スライドの凍結、60歳台後半の在職老齢年金の導入、総報酬制(ボーナスも含めた年収をベースとした保険料徴収)の導入、などが盛り込まれている。
厚生省による公的年金制度改正案をうけて、議論の舞台は政治の場に移された。99年2月26日、厚生省は公的年金制度改正案の大綱をまとめた。内容は先の公的年金制度改正案をベースにしたものである。
保険料負担については、景気の低迷を考慮して、厚生年金、国民年金の保険料の引き上げを当面の間凍結することとした。また、基礎年金に占める国庫負担の割合を現行の3分の1から2分の1に引き上げるとし、これを保険料引き上げ凍結の解除と同時におこなうとした。また、ボーナスも含めた年収をベースとして保険料を徴収する総報酬制が2003年度から導入されることとした。
年金給付については、厚生年金の報酬比例部分の給付水準を現行より5%削減するとした。また99年度から、年金を受け取り始めた後現役世代の可処分所得の伸びに応じて年金額を引き上げる賃金スライドを廃止、物価水準に応じて引き上げる物価スライドのみにするとした。2002年度からは、60歳台後半で働いて一定の所得があると年金が減額される在職年金制度を導入するとした。2025年度までに厚生年金の支給開始年齢を段階的に65歳まで引き上げるとした。このほか、政府としてどの程度の水準の年金を保障するのか、という目安として、現役世代の手取り年収のおよそ6割を確保するとの文章が加えられた。
現在、99年公的年金制度改正の論議は、連立与党を組む自民党と自由党の間で協議が難航している。自由党は、政策責任者協議会の中で、厚生省・自民党がまとめた大綱に盛り込まれている給付水準の5%切り下げの 削除を主張、また基礎年金の財源について将来的に全額税方式に切り替えることを盛り込むよう求めている。これに対して自民党は、給付水準を引き下げなければ将来保険料を引き上げざるを得なくなるし、基礎年金の財源を全額税方式にすることは社会保険方式と矛盾することになるため、自由党の主張には反対を唱えている。
一方、小渕首相のもと設立された経済戦略会議は、99年2月にとりまとめた答申のなかで、基礎年金は将来的に税方式に移行するべき、報酬比例部分は30年後に完全民営化するべき、とする公的年金制度改革案を提言している。
2. 確定拠出型年金導入についての最近の議論
日本の企業年金においては、加入した期間や賃金水準などに基づいてあらかじめ年金給付額が決まっている確定給付型年金のみしか認められていない。確定拠出型年金とは、拠出した掛金額とその運用収益に基づいて年金給付額が決まる仕組みである。確定拠出型年金としては、米国の401Kプランと呼ばれる課税繰り延べ制度が有名で、日本における確定拠出型年金導入の議論も、401Kプランを念頭において進められている。
401Kプランとは、内国歳入法401K項に基づく雇用者を対象とした税制適格の課税繰り延べ制度である。従業員は年間10000ドルを限度に課税前所得から掛金を拠出、事業主は従業員拠出とあわせて30000ドルまたは給与の25%を限度に上乗せ拠出(マッチング拠出)をおこなうことができる。拠出時、運用時は非課税で、給付時まで課税が繰り延べられる。積立金の運用方法は、プランで用意されたいくつかの方法の中から従業員自らが選択する。積立金の払出しは退職や一定年齢に達した場合などにおこなわれるが、それ以前に払出しを受ける場合は、ペナルティタックスが課される。給付形態は、一時金および年金のいずれかが選択できる。
日本で確定拠出型年金導入の議論が本格的に始まったのは、98年2月20日に自民党から出された緊急国民経済対策(第4次)のなかで、証券市場の活性化対策としてその導入を検討することが示されたのにさかのぼる。同年3月31日に出された規制緩和推進3か年計画のなかでは、確定拠出型年金について99年度中に結論を得るとされた。同年4月24日の総合経済対策では、雇用対策、および資金供給システムの変革、の項目のなかに確定拠出型年金の導入が盛り込まれた。同年6月には自民党の労働部会の下に設けられた確定拠出型年金等に関する小委員会が財形年金を日本版401Kに衣更えする提言をおこなった。
同年10月に自民党の年金制度調査会の下に私的年金等に関する小委員会が設置され、12月に提言がまとめられた。この中では、企業拠出型と個人拠出型の2種類の導入が提言されている。企業拠出型は従業員ごとに一定のルールで定めた額を企業が拠出し、運用は企業が一括運用、もしくは個人が運用を指図する。企業拠出型は、現行の厚生年金基金や税制適格年金からの移行・上乗せ・新設などの導入形態が想定されている。個人拠出型は個人が加入する仕組みで、対象者は雇用者または自営業者である。雇用者対象の個人拠出型は、給与からの天引きが可能で、財形年金の拡充という導入形態が想定される。このほか、雇用者の転職、離職時に税制優遇措置を継続できる個人勘定(日本版ロールオーバーIRA)を設けることが提言されている。
98年12月、大蔵・厚生・通産・労働の4省で構成される確定拠出型年金制度準備会議が設置され、99年6月までに具体案の取りまとめをおこなうこととなった。私的年金等に関する小委員会案をベースに検討が進められ、99年6月に原案がまとめられた。
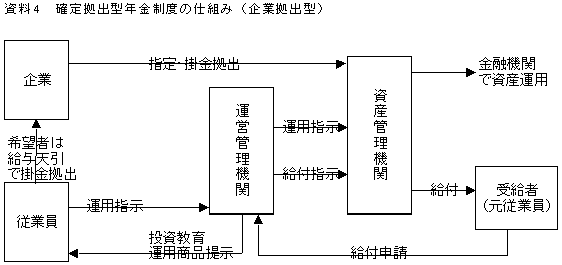
この原案において、小委員会案から議論が進んだ点は次のとおりである。
- 雇用者対象の個人拠出型は企業単位で残高管理するのに対して、自営業者対象の個人拠出型は国民年金基金連合会に保険料が払い込まれ、残高管理される。
- 受給形態として、年金のみでなく一時金は認められることとなった。
- 企業拠出型への個人の拠出が認められることとなった。ただし、今後次のポイントについて検討を要すると思われる。
- 米国の401Kプランでは従業員拠出に企業のマッチング拠出がおこなわれることが一般的で、そのことが401Kプラン普及に大きな役割を果たした。現在の案では個人拠出型への企業拠出が認められていないが、マッチング拠出を可能とする仕組みが必要ではないか
- 確定拠出型年金の導入を円滑に進めるためには、米国のERISA法のような企業年金法を整備し、受給権の保護、受託者責任の確立、従業員に対する投資教育の充実、などをはかる必要があるのではないか。