1. はじめに
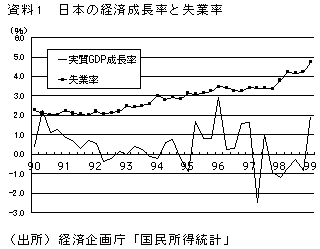 日本経済は、経済成長率が97・98年度と2年連続でマイナスになるなど、低迷を続けている。完全失業率は史上最悪を更新し、5%台にまで迫ろうとしている。こうした状況下、大規模な財政政策とゼロ金利という思い切った金融政策が続けられているが、日本経済再生のために政府が切れるカードはそう残されていない。
日本経済は、経済成長率が97・98年度と2年連続でマイナスになるなど、低迷を続けている。完全失業率は史上最悪を更新し、5%台にまで迫ろうとしている。こうした状況下、大規模な財政政策とゼロ金利という思い切った金融政策が続けられているが、日本経済再生のために政府が切れるカードはそう残されていない。
我々は、昨年7月に「年金改革に関する提言」をとりまとめ発表した。その内容は、公的年金を持続可能なものにするための基礎年金の税方式化と報酬比例部分の民営化、およびその受け皿となる確定拠出型年金を含めた企業年金制度の整備、についてであった。我々は今回、「日本経済再生の構図」という枠組の中で今一度年金改革についてとりあげた。これは、昨年以降ますます日本経済の容体が悪化していくなかで、年金改革こそが日本経済再生のために政府の切るべき数少ないカードの1つではないかと考えるからだ。
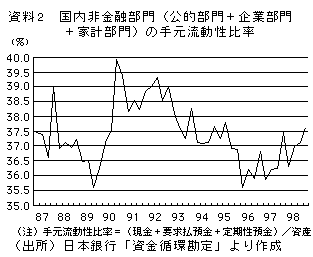 昨年以降の日本経済の悪化は、経済主体間における相互不信の深まりの過程であった。預金者と金融機関の間で、金融機関相互で、金融機関と事業会社の間で、事業会社相互でその支払いや決済に不信を募らせ、手元流動性を積み上げることが起こった。その後、昨年9月と今年2月の二度にわたる金融緩和、今年3月の7兆5000億円近い額の公的資金による銀行への資本注入、信用保証枠の拡充といった事業会社の資金繰り支援策等の結果、コンフィデンスの悪化には一応歯止めがかかったように思われる。この過程において我々は、日本的雇用慣行など経済主体間の関係を維持しつつ総需要の回復を待つという従来的な手法の崩壊を目の当たりにし、自らの再生への次なるステップは、不必要な部分を思い切って切り捨て必要なところに資源を集中する 「スクラップ&ビルド」という新しい手法であると気づくに至った。ここで、前者の手法とは従来型の公共事業、不良債権処理の先送り、株式持ち合いなどに代表され、後者の手法とは資源の再配分と考えることができよう。このところ、過剰設備・過剰債務の解消が議論されている。雇用についても、失業率が5%目前に迫るなか、次の景気回復局面を“jobless recovery”ととらえ、雇用温存型から新規雇用創出へ政策の軸足が移されつつある。これらのことは、まさしく「スクラップ&ビルド」による経済再生への第一歩とらえることができよう。
昨年以降の日本経済の悪化は、経済主体間における相互不信の深まりの過程であった。預金者と金融機関の間で、金融機関相互で、金融機関と事業会社の間で、事業会社相互でその支払いや決済に不信を募らせ、手元流動性を積み上げることが起こった。その後、昨年9月と今年2月の二度にわたる金融緩和、今年3月の7兆5000億円近い額の公的資金による銀行への資本注入、信用保証枠の拡充といった事業会社の資金繰り支援策等の結果、コンフィデンスの悪化には一応歯止めがかかったように思われる。この過程において我々は、日本的雇用慣行など経済主体間の関係を維持しつつ総需要の回復を待つという従来的な手法の崩壊を目の当たりにし、自らの再生への次なるステップは、不必要な部分を思い切って切り捨て必要なところに資源を集中する 「スクラップ&ビルド」という新しい手法であると気づくに至った。ここで、前者の手法とは従来型の公共事業、不良債権処理の先送り、株式持ち合いなどに代表され、後者の手法とは資源の再配分と考えることができよう。このところ、過剰設備・過剰債務の解消が議論されている。雇用についても、失業率が5%目前に迫るなか、次の景気回復局面を“jobless recovery”ととらえ、雇用温存型から新規雇用創出へ政策の軸足が移されつつある。これらのことは、まさしく「スクラップ&ビルド」による経済再生への第一歩とらえることができよう。
マクロ経済学の教科書に必ず登場する考え方に「一国の財・サービスの生産力がその国民の生活水準を決定する」というものがある。この考え方のもとでは、GDPは生産要素である労働と資本、およびそれを産出にかえる技術に依存する。ここで重要なことは、いかにして労働と資本を有効活用するかということである。政府が労働と資本の配分をコントロールすることによって成功を収めるのは難しい。政府がいつも正しい判断を下すとは限らないからだ。我々は、多様な参加者からなるマーケットにおいて試行錯誤を繰り返しながら結果として決まる労働と資本の配分が、実現可能な最もoptimalな資源配分ではないかと考えている。
このような労働と資本における「スクラップ&ビルド」のメカニズムが働くためには、労働市場 と資本市場が活性化されなければならない。我々が年金改革を日本経済再生のために政府の切るべきカードの1つと考えるのは、年金制度を持続可能なものにして将来不安を取り除くという視点だけではない。年金改革が、雇用の流動化を通じて労働市場の、投資行動の奥行きを広げることを通じて資本市場の活性化に重要な役割を果たしうると考えたからである。
本報告書では、労働市場 と資本市場の活性化という観点から年金改革の提言をおこなう。2では年金改革についての最近の議論を紹介し、3では確定拠出型年金導入について考え、4では我々の提言する厚生年金民営化について説明する。5ではここで提言する年金改革が日本経済再生にどのようにつながるかについて議論する。