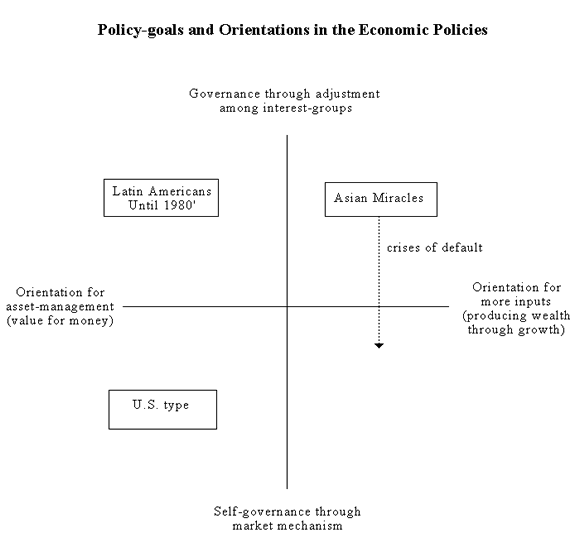「東アジアと反転攻勢の基地としての日本」
1998.3.5.
21世紀政策研究所
理事長 田中直毅
1. 日本の経済困難と東アジアに起きている現在の経済困難とは、同じ枠組みで議論できる。
80年代に日本は、バブルを発生させたため、現在、大変困難な状況に置かれている。このバブルは、利害調整による統治から、マーケットメカニズムを通じた自己統治への移行に失敗した中で発生した。
今日、日本政府は、ビッグバンという形で、金融システムの根本的な変革を目指しているが、その前に、公的資金を投入しなければ、金融システム不安を払拭できないという局面に立たされている。住専処理において大蔵省は、保守党政治家の利害により、農林系の金融機関の救済を迫られ、公的資金の投入を決めた。今日、日本において、公的資金の投入にこれだけ手間どっているのは、そうした利害調整による統治から、なかなか脱却できないためである。
翻って、「アジアの奇跡」は、利害調整による統治に基づき、成長を求めて投入財を次々用意するという仕組みの中で起こった。しかし、アジア経済が金融面において、国際秩序の枠組みの中に入った途端、それはうまく機能しなくなり、いくつかの国でデフォルトの危機に当面することになった。
2. 東アジアにおける経済混乱に対して日本からの主張が聞こえてこないという意見が聞かれる。日本はアジア向けの輸出に多くを依存しており、97年のアジア向け輸出は日本の全輸出の41%を占めている。このことからもわかるように、アジアの経済混乱が長引いて最も影響を受けるのは日本であり、日本として何らかのメッセージを送るのが当然であろう。しかし、日本の政策担当者はそれを躊躇してきた。その背景には、第一に、第二次世界大戦で日本が周辺のアジア諸国に対して行なった侵略行為を戦後も重く受け止め、経済運営といえども明確な意見を言わないという態度をとり続けてきたことがある。
第二は、東アジアにおける日本の銀行の与信は、米国の5倍以上ときわめて大きいにもかかわらず、現地に設立された日系の合弁企業に対するものが大宗を占めていることである。韓国だけは、日系企業の設立がきわめて限定的であるため、かなり状況が異なるが、貸金の回収にさほど心配はないという事情が、ある種の無感覚、無関心を形成しているのだと考えられる。
第三には、日本が行政改革をはじめとする日本の構造改革に忙殺されているということである。
3. これに対して米国は、80年代、きわめて積極的に、ラテンアメリカ諸国が抱えた問題をどうすれば解決できるかについて考え、メッセージを送り続けてきた。80年代のラテンアメリカ危機に対しては、米国議会も巻き込んだ取り組みがなされ、具体的にどう救済するのかの戦略が練られた。その基本は、ラテンアメリカ諸国の外貨建債務を返済させるために、各国の輸出を増やすということであったが、このことは、市場開放を完全に行なった米国が、ラテンアメリカ諸国の製品をどれだけ買い取れるかというテーマにほかならない。例えば、アルゼンチンが小麦を大量に輸出することは、債務返済のためには当然必要なことであるが、これによって、米国では、84年から85年にかけて小麦農家が倒れる事態が起きた。しかし、アルゼンチンにとっては、小麦を輸出する以外に債務を返済する手段はない。米国は、小麦農家が倒れてまでも、アルゼンチンの輸出増を受け入れたのである。さらに、米国は日本に対しても、ラテンアメリカの製品が入るよう市場開放を求めた。債務の一部棒引きについても、ブレディ・プランをつくり乗り出した。このように米国は、80年代の危機に対して、きわめて整合的・本格的にこの問題に取り組んだわけである。
94年のテキーラショックの際は、これよりは多少、自動的にメカニズムが働いた。為替の切り下げは起きたが、既にNAFTAが成立していたことから、メキシコを北米に対する輸出基地として活用しようと考えている人たちがおり、メキシコへの直接投資が進んだ。財政赤字が大きく、自分の身の丈を越えた形で消費をしているところに対して節約を要求するというIMFの処方箋は、メキシコのような政策運営を行なっているところには適切であり、みごとに実効を上げた。
4. 現在、東アジアにおける成長メカニズムは明らかに中断しているが、これは、成長のための戦略、すなわちグロウス・トライアングルが崩れたことを意味する。そのプロトタイプは、プラザ合意以降の日本企業が選んだグロウス・トライアングルである。1ドル=240円前後であった円ドルレートが、プラザ合意の後180円へと動いた際、日本の企業は、東南アジアを生産基地として活用して、対米輸出を図ろうと考えた。
おそらく、最初の成功例となったのはミネベアである。マーケットは依然として米国であったが、タイに工場をつくり、米国での需要に応じて、タイから次々にチャーター機を飛ばし輸出するという形のトライアングルをつくりあげ成功した。この成功体験がコピーされ、多くの日本の製造業が、オフショワ・プロダクションの基地として東南アジアを選び、トライアングルをつくっていたわけである。この仕組みが原型となり、東アジア諸国にある様々なリソースをうまく組み合わせれば成功できるというグロウス・トライアングルが次々に形成されたのである。
このことは、サダム・フセインのクエートに対する侵略で、より明確になる。一つの仮説であるが、東アジアにもう一人のサダム・フセインが登場するかもしれないと考えた人が相当いて、その登場を抑えるために考えられたのが、隣国と共存することにより大きな成果をあげるグロウス・トライアングルであったのである。例えば、シンガポールが、グロウス・トライアングルをインドネシア、マレーシアとの間につくる。台湾も、香港を通じて直接中国本土に投資を行ない、グロウス・トライアングルをつくる。結果としてこうしたグロウス・トライアングルが次々に登場する中で、「アジアの奇跡」が演出されていったのである。ところが、今日の通貨・金融危機により、こうしたグロウス・トライアングルは、ほとんどすべて断たれるという事態に陥っている。
5. 東アジアが経済調整に取り組み、経済を回復させるということは、日本自身の問題である。東アジアをどう支えることができるかということは、実は、自分自身の力で日本をどう支え得るかということなのである。このことを考えるとき、80年代前半、ドル高のもとでの米国と、これからの日本を対比することは、きわめて興味深い。80年代前半のドルと同様に、円は今日、周辺諸国の通貨に対して、大幅に上昇している。「喪失の10年」といわれた80年代のラテンアメリカに匹敵する「喪失の10年」が今、東アジアにも訪れたと認識すべきであるが、この状況も、当時の米国と同じである。
米国はドル高のもと、国内市場を完全に開放したが、日本が米国と同じ道を歩むのかどうかは興味深い。米国は市場開放の結果、製造業の空洞化を招いた。現在、カラーテレビの生産は、米国内で一切行なわれていない。このことに代表されるように、完璧な市場開放を通じて、アメリカの産業は根底から変わった。そして今、日本が変われるかどうかが問われているのである。また、米国の場合、財政と貿易の双子の赤字を続けた。現在、日本は財政赤字の状態にあるが、双子の赤字に至るのかどうかについては未だ明確にはなっていない。さらに米国は、ラテンアメリカ経済を正常化させるために、強い内需を背景として、外国資本の還流に直接取り組んだ。日本はこうした取り組みができるかどうかが問題とされる。東アジア諸国が債務を返済して、再び各国の内部で投資が行われる条件をつくり出せるかどうかについては、依然として疑問符がついたままである。
6. 日本の経済政策は、東アジアの経済発展に対しどのような役割を果たすのかという視点から、今一度見直される必要がある。橋本首相は財政再建にこだわっているが、そこには、それなりの根拠があるのも事実である。日本の財政状況がきわめて悪化しているのはそのとおりであり、橋本首相は財政構造の再建は重要かつ喫緊の政策課題であると判断され、自民党もそうした路線に乗った。そのため、財政構造改革会議という、今までにないシステムが導入され、これまで聖域とみられていた社会福祉支出についても抑制する仕組みがつくられた。
したがって、財政再建に向けた努力は、日本のジェネラル・ガバメントを再建するうえで不可欠な努力であると思われる。ただし、昨年の後半以降、東アジアで需要の崩壊が起こり、これをそのまま放置すれば、東アジア諸国は少なくとも5年以上はかつての成長経路に復することはできない。そうした事態に対処するためには、日本の市場を開放すると同時に、彼らの製品を吸収できるよう内需を拡大する必要がある。
そうした政策追及の結果として、財政バランスが短期的に悪化したとしてもやむを得ないのではないか。ただし、その場合でも、かつてのような利害調整を前提として日本列島に仕事を配るために公共事業を増やすという方策は好ましくないのはいうまでもない。バリュー・フォア・マネーを実現するという観点から内需喚起策を検討する必要がある。
7. 東アジアの経済調整が短期間に収束できるかどうかは、自由貿易協定に相当するべきものが域内で確立し、日本が各国から財を受け入れることができるかどうかという点にかかっている。それができれば、東アジアの産業再編は可能となる。そうした動きの中で、日本に対する輸出基地として東アジア各国が位置づけられ、東アジアに対する直接投資が世界から起こるであろう。こうした流れをつくる以外に、短期間に東アジアの経済調整を収束させることはできないというのが、私の見方である。
また、輸出の振興、直接投資の増大を図るためには、東アジア諸国が現在直面している金融問題を早急に解決しなければならない。例えば、国内金融の円滑化を促進するためには預金者の不安心理を解消する必要がある。そのためには、預金者保護のために投入される公的資金についてはIMFの財政再建計画の枠外とするという方策も検討に値しよう。また、為替レートの安定化のためには、東アジア通貨売りに偏した外国為替市場における需給情勢を改善することが求められている。こうした観点からも、東アジア版ブレディプランについて広く検討する必要がある。
資料1
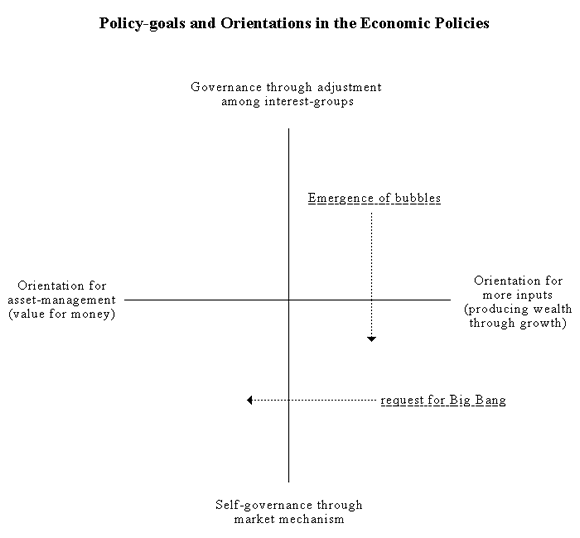
資料2